切っても切っても生えてくる
強い生命力が スタミナ源に!
強い匂いが うまみのもとに!
にら(韮)
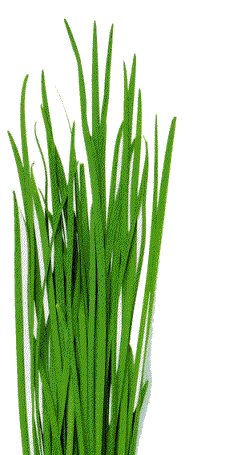
● スタミナ野菜 にら[韮]
切っても切っても次から次へとどんどん生えてくる、強い生命力。
ユリ科の多年性植物です。
強い匂いがうまみのもと。
寒い冬に体を温めスタミナをつける旬野菜・ニラを召し上がれ。
臭気の強い野菜は刺激があるため辣(ら)と呼ばれますが、食べておいしいので美という文字をつけ、美辣(みら)といいます。
ニラは小さいので小美辣と称され、転じてニラになったといわれています。
東アジアの各地に自生し、中国や東南アジアでは古代から栽培されています。
ところがヨーロッパでは現在でもほとんど栽培されていません。
日本では、古事記や日本書紀にも記述があり、万葉集には”久々美良”として登場。このみらがなまって、ニラとなったという説もあります。
北海道や東北などの寒い地方では、体が温まり精力がつく野菜として、古くから重宝がられていました。
ニラは丈夫でつくりやすく、刈り取った後の株から再び新葉が伸びて、年に数回の収穫が可能です。
戦前は家庭菜園での栽培が主で、あまり八百屋さんの店頭には並びませんでした。
現在では、強いにおいもあまりきらわれなくなって消費が伸びています。
北海道から沖縄まで全国的に栽培されるようになりました。
◆ニラの旬は冬から春
冬から春にかけてのものは葉肉が厚く柔らかです。
出回っているものの大半は、葉幅が広く色も濃い”グリーンベルト”です。
夏には暑さに強い細葉種も出回り、一年中手に入ります。
主な産地は栃木、高知などで、全国の出荷量の約6割をこの両県で占めています。
”テンダーポール”という花にら用の品種は、5月から10月にかけて次々に花のつく茎を伸ばします。
つぼみと茎を食用とします。
◆ニラの種類
青ニラ
大葉種のグリーンベルトが一年中出回るが、11~4月がいちばんおいしい。
黄ニラ
青ニラと々品種ですが、ニラの芽が出る前の根株に黒いビニールを覆いを被せて光をさえぎって、もやしのように育てる軟白化した栽培で、やわらかく黄色になります。別名ニラもやしともいいます。
ニラ特有の臭みがなく、香りは淡く上品で、ほのかな甘みが有ります。
高級な中国料理に使われます。
日本では岡山県が主産地です。
花ニラ
ニラの花茎と若い蕾を食べる中華料理の食材で、晩春と秋口が旬になります。
一般に見る青ニラネとは別品種で、花ニラ専用の品種が栽培されています。
日本で主に栽培されているのは、台湾から伝わったテンダーポールという栽培品種です。
とう立ちした花茎を食べます。
シャリッとした歯ごたえの油いためがおいしい。
● 古くて新しい野菜 ニラ
にらは中国西部原産の野菜です。
東アジアの各地に自生していますが、にらそのものはヨーロッパにはない野菜です。
日本のにら栽培の歴史は平安時代の記録に記されるほど古く、古事記では「加美良(かみら)」、万葉集では「久君美良(くくみら)」として登場。
「にら」という名は、おいしいという意味の古語「美良」(みら)が変化(子音交替)した言葉といわれています。
江戸時代には、薬用として利用されており、食用として利用されるようになったのは、明治時代に入ってからです。
戦前は家庭菜園での栽培が主で、あまり店頭には並びませんでした。
野菜として消費が増えたのは戦後。
現在では、ビタミン豊富で栄養価の高いスタミナ野菜として健康志向を背景に消費が伸びています。
品種と栽培方法の改良で、北海道から沖縄まで全国的に栽培されるようになっており、一年中手に入りますが、1~5月の入荷量が比較的多く、旬は春先から初夏にかけてです。
にらは、葉を利用する葉にら、光を制限して軟白栽培する黄にら、つぼみのついた若い花茎を食用とする花にらに大別されます。
葉にらの品種は、葉幅が広い大葉にらと、細葉の小葉にら(在来種)に分けられます。
昭和28年に発売されて以降長い間流通の大半を占めていたのは、大葉にらの中でも葉幅が広く、やわらかさが特徴の‘グリーンベルト’でしたが、近年はさらに葉幅が10%程度広く収量の良い‘スーパーグリーンベルト’や収穫調製がしやすい‘ワンダーグリーンベルト’などが多く出回っています。
野菜全体の生産量が減少傾向にある中、にらの作付面積は近年増加傾向にあります。
周年生産が可能なことから収益性も良く、価格も非常に安定して作りがいのある野菜になっています。
今後ほうれんそうとともに、機能性の面からもますます需要増加が期待できる野菜といえます。
● ニラの栄養と機能性
◆ 老化予防に最適!
ニラー束(100g)には、老化防止に役立つカロテンが豊富に含まれている他、ビタミンB1、B2、C、Eといったビタミン類、カルシウム、カリウムなどのミネラルなど、様々な栄養素がバランスよく含まれている緑黄色野菜です。
ビタミンAの含有量は、100g中3,500ugと緑黄色野菜の中でも多く、皮膚や粘膜を丈夫にして抵抗力を高める効果が期待できます。
疲労回復に効果的なビタミンB1やエネルギー代謝を促すビタミンB2もバランス良く含むことから、にらはビタミンが豊富なマルチビタミン野菜といえます。
ニラ独特のあの強いにおいは、ネギやタマネギにも含まれる辛味成分「硫化アリル」によるものです。
硫化アリルには、ビタミンB1の吸収力を高める効果があるので、スタミナ増強を目指す方にオススメ!
強い抗酸化力を持つビタミンEや止血したり骨を丈夫にするビタミンK、コラーゲンの生成や保持などの働きがあることから美肌効果や風邪予防効果のあるビタミンC、胎児の正常な発育に重要で認知症予防効果のある葉酸も豊富に含まれます。
ニラの精力増進作用は、男女を問わず生殖器の働きに活力を与え、その機能を活発にします。
胃腸の機能を増進し、血液の循環を促して、体の諸機能に活力を与えます。
新陳代謝を促進、食欲増進、夏バテ解消、風邪の予防、血液の流れをよくするなどの効果も期待できます。
また、足腰の衰えやだるさ、インポテンツ、慢性便秘、冷え症にもすぐれた効果があることが知られています。
また、ニラは肉や魚の生臭さをやわらげてくれるうえ、カロテンとビタミンEは油と一緒に食べると吸収力がアップ!
つまり、レバーなどの肉類と炒めるのは非常に理にかなった調理方法なのです。
◆ ニラの強烈な香りのもとはアリシン
にらは強い香りがあるため、金曜日に売り上げが伸びる週末野菜とも言われています。
にらの強烈な香りは、アリシンというにんにくやねぎにも含まれる硫化物の一種によるものです。
アリシンは、消化液の分泌を促し、内臓の働きを活発にする働きがあるため、食欲不振、胃もたれを解消する効果があります。
また、自律神経を刺激して新陳代謝を活発にする働きがあるため、血行を良くして体を温め風邪に効くとも言われています。
そのため、風邪をひいたときに「にらがゆ」を食べるのは効果的です。
そのほか、ビタミンB1の吸収を助けて効力を持続させる働きがあり、豚肉やレバーと合わせると消化吸収が良くなります。
豚肉とにらの炒め物、にらレバ炒めなどは、栄養的にも根拠のある料理と言えます。
さらに、アリシンには血液を固まりにくくする働きもあります。
血栓ができにくくなるので、脳や心臓に起こる疾病のリスクを低減する効果が期待できます。
このように、にらの強烈な香りのもとであるアリシンは様々な機能性を有します。
● おいしいニラの選び方・保存法
葉の幅が広く、やわらかいにらを選びましょう。
根本の切り口が新しく、葉の色つやがよく、葉先までピンと伸びているものが新鮮です。
葉先が折れたりしおれているものや、葉に白い斑点があるものは避けましょう。
ニラは傷みやすいので、買い置きは避け、早めに食べきりましょう。
冷蔵庫で保存する場合は、一度しおれると水につけても戻らないので、葉先が折れないようにラップできちんと包み、葉が重ならないように冷蔵庫の野菜室に立てます。
冷凍保存する場合は、洗った後適度な長さに切り、キッチンペーパーなどでよく水気を取ってからタッパーや保存袋などの密閉容器に入れて保存しましょう。
● ニラの調理・食べ方
にらは、炒め物、鍋物、スープなどいろいろな料理に合います。
肉やレバー、貝類、卵などの動物性食品と相性が良いので、卵とじや野菜炒め、にらレバ炒め、ギョーザ、春巻きなどがおすすめです。
調理のヒント
水気がついていると腐りやすいので、調理前の水洗いは手早くしましょう。
また、あらかじめ切っておくと、酵素の作用で、臭いがきつくなるので、調理の直前に切りましょう。
にらは葉先と根元で含まれる栄養成分が大きく異なるため、切り方を変えると栄養を効果的に摂取できます。
根元の白い部分にはアリシンが豊富に含まれており、細かく刻むと、アリシンが増加します。
これに対し、葉先にはカロテンやビタミンEが豊富に含まれていますが、これらの栄養素は切ったり炒めたりする過程で失われやすいので、電子レンジで丸ごと加熱すると栄養を逃がさず甘くおいしくすることができます。
細長くまっすぐに伸びた葉は柔らかく、汁の実や薬味、おひたしの他、中国料理や韓国料理に用いられます。
単独や他の野菜や肉と合わせた炒めもの、中でも、レバーと炒め合わせた「ニラレバ炒め」は多く知られ親しまれるところです。
また、餃子の具、ニラ饅頭、チヂミ、ニラの卵とじなどがポピュラーな料理用途です。
岡山県では、黄ニラが寿司の具としても用いられています。
栃木県鹿沼市などでは、蕎麦の具として茹でたニラを添えた、ニラ蕎麦があります。
若い花芽もおひたしや炒め物として食べることが出来ます。
硫化アリルは、揮発性で水溶性ですから、切る、洗うなどの動作は、手早く行わないといけません。
また、加熱時間が長くなってしまうと、色が悪くなるばかりか、風味も落ちてしまいますから、加熱は、サッとが基本です。
● ニラ玉
ニラを炒めて、味付けした溶き卵を流し入れて作ります。
卵とニラの絶妙な組み合わせで、簡単でとてもおいしいニラ玉のレシピ。
【材料】(2人分)
・ニラ 1/2束 ・卵 2個 ・塩 一つまみ ・しょうゆ 小さじ1/4
・ごま油 大さじ1/2
【作り方】
1、ニラを洗い、3cm幅ぐらいに切る。
ボウルに卵を割って塩、しょうゆを加え、ほぐしておく。
2、フライパンにごま油を熱し、にらを入れて炒めお好みで塩を軽くふる。
3、卵を加えて、やさしくかき混ぜる。
【メモ】
・ニラといっしょにキムチやもやしを加えてもおいしいです。
・お酒のあてにもいいです。
● ニラレバ炒め
【材料】(2人分)
・鶏レバー 150g ・ニラ 1/2束 ・しょうゆ 大さじ1/2
・ごま油 大さじ1/2 ・オイスターソース 大さじ1
【作り方】
1、ニラは端を落とし、4cmぐらいの長さに、ざく切りする。
鶏レバーはすじや血をきれいに掃除して切り分け、
ボウルに入れてやさしく流水でもみほぐすように洗い、10分ぐらいつけておく。
2、1の鶏レバーを熱湯で茹で火を通して取り出し、しょうゆをかける。
3、フライパンにごま油を熱して2を炒め、オイスターソースで味をつける。
4、にらを入れてさっと炒め合わせる。
● ニラ卵スープ
【材料】(4人分)
・ニラ 1/3把 ・卵 3個 ・中華スープ 6カップ
・片栗粉 大さじ2 ・ごま油 小さじ1
A・・・醤油 小さじ2 ・塩 小さじ1/2 ・こしょう 少々
【作り方】
1、卵は割りほぐし、ニラは5㎝に切る。
2、中華スープをAで調味し、水溶き片栗粉でとろみをつける。
3、スープが暖まったら卵を流し入れ、ニラを加え、
仕上げにごま油で香りつけする。
● 納豆とニラの包み揚げ
【材料】(4人分)
・納豆 1パック ・ニラ 1/2束 ・粉チーズ 大さじ2
・しゅうまいの皮 12枚 ・揚げ油適宜
【作り方】
1、ニラは細かく刻みます。
2、ボウルにニラと納豆、粉チーズを入れてよく混ぜ合わせます。
3、しゅうまいの皮の中央に2をのせます。
皮の端に水をぬり、4つの角を真ん中で合わせて閉じ、
皮の端と端を指で押さえつけます。
4、揚げ油を170℃に熱し、③を入れてカリッと揚げます。
● ニラレバチャーハン
【材料】(2人分)
・牛レバー(またはとりレバー) 100g ・ご飯 茶碗2杯分 ・ニラ 1/2把
・豆板醤 小さじ1/2 ・生姜のみじん切り 大さじ1
・しょうゆ、サラダ油、塩、こしょう 適宜
【作り方】
1、牛レバーは1cm角に切ってしょうゆ小さじ1と1/2、
豆板醤をもみこんで下味をつける。
2、ニラは1~2cm長さに切る。
3、フライパンに油大さじ2としょうがを入れて火にかけ、
香りが出たら1を加えて炒め、火が通ったら
ご飯とにらを加えて炒め合わせる。
塩、こしょう各少々で調味する。
● にらの話
森下敬一 『食べもの健康法』 より
昔から、北海道や東北地方などでは、ニラを盛んに食べてきた。
それというのも、ニラにはすぐれた保温作用があるからだ。
ニラを刻みこんだ味噌汁や雑炊をたびたび食べていると、耐寒力がうんと高まる。
それと同時に、冷え性、寝小便、神経症、シモヤケなど、冷えから来るいろいろな障害もすっかり治ってしまう。
そればかりか、ニラには、生殖腺の機能も盛んにする作用もあるので、性的能力も大いに増強される。
特に、男性の性機能の強化に役立つことから「起陽草」という別名もつけられているほど、精力減退や早漏などに卓効をあらわすのである。
このニラも、戦前は、東京の八百屋ではみられなかった。寒冷地の人たちに愛されたニラも、その特有の臭気のために、都会人には敬遠されたわけだ。
しかし、この臭気成分には硫黄質が含まれているので、すぐれた殺菌・防腐作用を表す。腸内に有害細菌が繁殖するのを防止するのである。
加えて、ニラの揮発成分は、胃壁を刺激して胃液分泌を促し、繊維は腸の働きを盛んにする。このため、ニラは腹痛や下痢症に卓効を表す。
消化機能障害を根本的に直し、体力回復を促すのである。
ともあれ、食品公害時代に生きる現代日本人は胃腸機能が大きく狂わされているから、健胃・整腸効果の大きいニラを大いに利用すべきだ。
胃腸機能の失墜こそ、すべての慢性病の元凶なのである。
また、ニラには、カロチン、ビタミンB1、B2、Cなどが豊富に含まれているが、食べることによってビタミンB1の補給効果が飛躍的に大きくなるという特性を持っている。
熱によっても破壊されにくいビタミンCが、B1の吸収をよくする上に、臭気成分である硫化アリルがB1と結合して、B1の吸収や体内保留を助けるからだ。
ビタミンB1を十分に補給することは、穀物中心食であるわれわれ日本人にとって、特に重要である。澱粉質をスムーズに代謝して、エネルギーを効率よく生産するためにはB1が大量に必要だ。
白米や精白小麦製品を常食していると、例外なくB1欠乏になるから、せいぜいニラを食べるべきだ。
ニラは懶人草(らんじんそう)ともいわれる。懶とは、なまける、めんどうくさがるの意。
一年中栽培できるし、摘めば次々と新芽が出てくるから、なまけ者がつくる野菜としてはもってこい、というわけである。
ニラは葉緑素や鉄もたっぷり含まれているから、貧血に有効で、鼻時の出やすい体質にも有効だ。
また、不眠症の人はニラを枕元において匂いをかぐとよい、ニラをもんだ汁をつけると止血効果がある、痔にはニラを煎じた汁で患部を洗うと有効・・・・・・といった即効的効果もある。
■ にらのごまみそ
材料(4人分)
・にら・・・300g ・油揚げ・・・2枚 ・しょうが・・・1かけ ・黒ごま・・・大さじ2
・ごま油・・・大さじ3と小さじ1 ・だし汁・・1/2カップ ・麦みそ・・・大さじ2
・自然酒・・・大さじ1 ・みりん・・・大さじ1と1/2
作り方
①にらは5cmに切り、油揚げは熱湯で油抜きして水気を取り、千切りにし、しょうがも千切りし、黒ごまは香ばしく炒っておきます。
②ごま油大さじ2杯を熱し、しょうがを炒め、次ににらを加えて塩少々で炒めて取り出し、さらにごま油大さじ1杯で油揚げをサッと炒めます。
③ごま油小さじ1杯、だし汁、みそ、自然酒、みりんを合わせて弱火でよく練ります。
④にらと油揚げを、器に盛りつけ、③のごまみそをかけて召し上がってください。

石川県認定
有機農産物小分け業者石川県認定番号 No.1001