�N�Ԃ̉��x����60��
�G�{�̗��E�k�C��������
�u�����E��������Ă��n�̉�v
�i�`�r�L�@��͔|
�k������
��
�j��
�@
�@
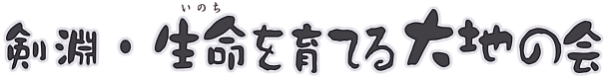
�@
��������Ă��n�̉�ł́A
����_�Ƃ̂���JAS�F���擾���Ă��܂��B
�@

�@
���w�_��A�����܂��g�킸�Ɉ�Ă��A
�u���S�Ɛ^�S�v�̔_�앨�ł��B
����̊��g�����傫���ق�
�Â݂�h�{�f����������~������
�����̂��Ⴊ�����́A
�@��o���ꂽ����̐V�N���B
�@
�ς�����͑�������܂����̒ʂ肪�悭�A
�z�N�z�N���Ă���̂ŃR���b�P�ɍœK�B
�ق�̂���ꂽ�ϕ��ɂ���Ɩ������݂�
���ɔ��������o���オ��܂��B
�ӂ����Ă��̂܂ܐH�ׂ�̂����������B
�A�c�A�c�̃W���K�C���Ƀo�^�[���̂���A
���Ⴊ�����̑f�ނ̖���
���̂܂����オ��܂��B
�@
���@�k������

�@
�L�^�A�J���͒j�݂����ǂ����i��ŁA
���F�͉��F���ۂ��S���������邶�Ⴊ�����ł��B
�܂��̖����u�����j�݁v�Ƃ������܂��B
�܂��A�Â݂�����z�N�z�N�ƕ����ӂ����Ƃ���u�I���Ⴊ�v�Ƃ��Ă�܂��B
�@
���a62�N(1987)�k�C���̗D�Ǖi��ɑI�ꂽ���Ⴊ�����̃G���[�g�ł��B
������ƌ��A�j�݂����݂����Ȏp�ł����A��Ŕ����ɐ��Ă݂Ă��������B
�����j�݂̕ʖ��͈ɒB���Ⴀ��܂���I�I
�H�~�������鉩���F���ق�Ƃɂ����������B
���������͂������ł����A�h�{�ɂ����ځI
�r�^�~���b��J���`���̊ܗL�ʂ������̂Ŕ��e�⌒�N���C�ɂ�����ɂ��œK�ł��B
�@
�����Ԗk�C���̓y�̒��ň�Ă�ꂽ�����̂��Ⴊ�����́A
�@��o���ꂽ����ŐV�N�B
����̊��g�����傫���قNJÂ݂�h�{�f����������~�����邶�Ⴊ�����́A
�k�C���̑�n�Ō��C�ɒa�����܂��B
�@
���Ⴊ�����ɂ̓r�^�~��C���L�x�B
�Ƃ��ɃL�^�A�J���ɂ͑����܂܂�܂��B
���܂��ɂ��Ⴊ�����̂ł�ՂɎ���ĉ��M���Ă����ɂ����̂ł��B
�L�^�A�J���͎ς����ꂵ�₷���̂ŁA�Ԃ��ă|�e�g�T���_��X�[�v�ɍœK�B
���ʂ�₷���̂ŗ������Z���Ԃōς݁A
�T�������b�v�������ă����W�Œ������ȒP�ł��B
���Ƃ̑������ǂ��̂Ŕ���̂܂ܑf�g�����Ă������������Ⴊ�����ł��B
�@
������������̗���
���a50�N(1975)�ɖk�C���_���ɂ����āA�W���K�C���V�X�g�Z���`���E�ɒ�R���̒����p�i��̈琬��ڕW�Ƃ��āA�u�j�ݏ��v���A�W���K�C���V�X�g�Z���`���E��R���́u�c�j�J�v�Ƃ��Č�z���A���a62�N(1987)�ɖ����o�^���ꂽ�����p�i��ł��B
���O�̗R���͈琬�n�̖k�̑�n�������Q�������]�Ɩ��邳��\�����Ă��܂��B
�@
�H�����ǂ����Ƃ�r�^�~���b���������Ƃ�����҂ɂ����X�ɒm���n�߁A�k�C���ɂ����镽���P�R�N(�Q�O�O�P)�̍�t�ʐς͂P�C�W�U�U�����ɂȂ�܂����B
�u�����j�݁v�u�I���Ⴊ�v�Ȃǂ̖��Ŕ����Ă��邱�Ƃ�����܂��B
�@
���i������
�����̌`�͝G���`�ŁA��F�͉��F�Ŗڂ̕����ɐԎ��F�̒��F����܂��B
�\��́u�j�ݏ��v���e�����ߊO���ɏd���������s��ł́A���g�̕i�����D��Ă��銄�ɂ͕s���Ȃ��Ƃ������B
���́u���[�N�C���v���Z�����F�ł��B
�@
�Ϗオ�肪�����A�ς�����̒��x�́u�j�ݏ��v����⑽�����ł��B
�ゴ���͂�⊊�炩�ł��B
�����㍕�ς͂���܂���B
�H���́u�j�ݏ��v�������ǍD�Ȓ��̏�ŁA���������Ȃ���₳�܂����Ɏ����ǂ����肪���܂��B
������������ƐH�����ቺ���₷���Ƃ����܂��B
�@
�p�r�́A�T���_�A����ŏ�������A���ӂ��Ƃ�����A�܂��A�X�[�v�Ȃǂ̂�����O�H�Y�Ƃɂ������Ă��܂��B
�@
�ς����ꂵ�₷���̂Œ����Ԏύ��ޗ����ɂ͕s�K�ł��B
�d�q�����W���M�͍���������Ƃ��ł��Ďς�����̐S�z���Ȃ��̂Łu�L�^�A�J���v�ɓK���������@�Ƃ����܂��B
�J���`���ܗL�ʂ������A�r�^�~���b�́u�j�ݏ��v�̖�1.5�{�߂��܂܂�Ă��܂��B
�@
���@�L�^�A�J���̔�t���t���C�h�|�e�g
�T���_�I�C���ɂ����^�ɐ����W���K�C�������Ă���ɂ����A
�����N���オ���Ċp�������Ȃ������x�����グ�܂��B
�T���قǒu���āA���x�͖���M���A���������ČϐF�ɂȂ�����o���オ��ł��B
������Ƒ������ȁE�E�Ǝv�����炢�����ɂȂ��Ă������ɂȂ��Ȃ�Ǝv���܂��B
���܂ɉ������ėp�ӂȂ����Ă����āA�g�����Ă����Čy���U����Ă��������B
�@
���@�L�^�A�J���̃R���b�P
�k����������Ĕ炲�Ƃ�ł܂��B
���̊ԂɁA�Ђ����E�ʂ˂��E�l�Q�E�Ƃ����т��u�߂ĉ��R�V���E���܂��B
�ʂ˂��E�l�Q���ԂƂ��āA�x�[�R����n���A�ق��������Ȃǂ�OK�B
�M�������ɂ��Ⴊ�����̔���ނ��čr���Ԃ��āA�u�߂�����������ݑe�M���Ƃ�A
�����݂̎c�邤���Ɋۂ߂čX�ɗ�܂��܂��B
�������E�n�����E�p���������āA���ːF�ɗg���܂��B
�H�ׂ�Ƃ��ɂ�����̂̓\�[�X����Ԃł����A
�卪���낵�ɏ��˂�����������ŕʎM�œY���āA�|���|�������Ă�Good
�@
���@�L�^�A�J�����u�߃W���K
�W���K�C���̓}�b�`�_���炢�̍א�ɂ��āA���ɂ��炭�N���܂��B
�N���Đ��Ȃ��ƁA���M���ɂł�Ղ��o�Ă��āA��������u�ߏオ���܂���B
�傫�ڂ̓炩���ȂׂɁA���߂ɖ������M���A
�߂ɃU�N�肵�����˂����u�߂āA�˂��̍��肪�o����A
�����悭�����W���K�C������C�ɂ���āA�傫�����������A
�����Ȃ��܂��Ȃ���A���R�V���E��U��A�W���K�C���S�̂̐F���ς��n�߂���A
�������~�߂܂��B
�]�M�Œ��悭�_�炩���Ȃ�̂ŁA�����Ȃ��瑁�߂ɉ��~�߂�̂��Ɉӂł��B
�]�M�Œ��悭�_�炩���Ȃ�̂ŁA�����Ȃ��瑁�߂ɉ��~�߂�̂��Ɉӂł��B
�@
���@�L�^�A�J���̃O���^��
�P���̉����ł�����������ۂ��Ǝς�i�P�T�����ڈ��j
��Ƀo�^�[�����A���o�Ă��Ă�A�j���j�N���u�߁A
�i�o�^�[���ł����Ȃ��悤�Ɏ�j�X���C�X����������������u�߂�
�i���ɂ͂��炳�Ȃ��ł����j�B
��������Ȃ肵����A�����E���N���[���������Ďύ��݁A
�Ƃ�݂��o�Ă��Ă�A���E�����傤�e���X�Ŗ��t��
�R�ɕ��ӂ���ԂɂȂ����P�����A�\�[�X�Ƃ���܂��ăO���^���M�ɓ���A
�Q�O�O���̃I�[�u���łQ�O�`�Q�T���Ă��Ċ����I�I
�@
���@�L�^�A�J���̂��D�ݏĂ�
�y�ށ@���z
�E���Ⴊ�����i�L�^�A�J���j�E�E�E600���@�E�ʂ˂��E�E�E��1�@�E�����G�r�E�E�E�P�T��
�E������E�E�E�R�{�@�E�C�J���E�E�E�P�p�C�@�E�����L�E�E�E�U�@�E�؋�����E�E�E�S��
�E�T���_���E�E�E���X
�E�g�b�s���O�E�E�E�g�V���E�K�A�\�[�X�A�}���l�[�Y�Ȃ�
�y�����z
�@�L�^�A�J���̔��ʂ͐��A�ʔK�݂͂����B
�C�J�A�z�^�e�͐H�ׂ₷���傫���ɐ�B
�ؓ���1����4�����ɐ�B
�A�ؓ��ȊO��S���{�[���ɓ���āA
�c��̃L�^�A�J�������肨�낵�ă{�[���ɉ����A
�S�̂��悭�Ȃ��܂��ă^�l�̏o���オ��B
�B�t���C�p���ɃT���_����M���^�l�̔��ʂ����A
�I�^�}�Ȃǂŕ\�ʂƎ���̌`�𐮂��ؓ��W�������
�t�^�����Ē��ŏĂ��F�����Ă�����Ђ�����Ԃ��A���ʂ�܂ŏĂ��B
���M�Ɉڂ��āA���D�݂Ńg�b�s���O�����ďo���オ��B
�y�����|�C���g�A�h�o�C�X�z
�g�p���邶�Ⴊ�����̓L�^�A�J���̕������ʂ�₷���̂Œ������Ԃ��Z���čς݂܂�
��ނ͊e���ƒ�ōD���Ȃ��̂����Ē����y���߂܂�
����F�����Ă݂Ă���������
�@
�@
���@�j��

�@
�j�݂͖����S�O�N�ɃC�M���X����k�C���ɓ������ꂽ�i��ŁA�k�C�����\���邶�Ⴊ�����ł��B
�z�N�z�N�Ƃ������������A�S��̏��Ȃ��i��ŁA���L�������Ɏg���܂��B
���F�͔��F�ł�╲���A�ł�Ղ𑽂��܂�ł��܂��B
�����Ԗk�C���̓y�̒��ň�Ă�ꂽ�����̂��Ⴊ�����́A�@��o���ꂽ����ŐV�N�B
�@
����̊��g�����傫���قNJÂ݂�h�{�f����������~�����邶�Ⴊ�����́A�k�C���̑�n�Ō��C�ɒa�����܂��B
���Ⴊ�����̓r�^�~��C���L�x�B���܂��ɂł�ՂɎ���ĉ��M���Ă����ɂ����̂ł��B
�@
�ς�����͑�������܂����̒ʂ肪�悭�A�z�N�z�N���Ă���̂ŃR���b�P�ɍœK�B
�ق�̂���ꂽ�ϕ��ɂ���Ɩ������݂Ĕ��ɔ��������o���オ��܂��B
�ӂ����Ă��̂܂ܐH�ׂ�̂ɂ������Ă��܂��B�A�c�A�c�̃W���K�C���Ƀo�^�[���̂���A���Ⴊ�����̑f�ނ̖������̂܂����オ��܂��B
�@
�@
�@
���@�u�����E��������Ă��n�̉�v��
�@
�������́A���삩�炳��ɖk�֖�50�L���A�ԂŖ�P���Ԃقǐi�ނƁA����~�n�̓�[�Ɉʒu������u�G�{�̗��v�������ɒ����܂��B
�������Ȃ��炩�ȋu�˂Ɉ͂܂�Ă��āA�Ă͂R�O�x�Ɣ�r�I�����A�~�͐Ⴊ�����������}�C�i�X�R�O�x�ƁA�N�Ԃ̋C�������U�O�x�ɂ��Ȃ钬�ł��B
�@

�@
�������̗R���́A���n�Ɉ炿�₷���u�͂�̖v�����������Ă����Ƃ����Ӗ��̃A�C�k��u�P�l�j(�͂�̖�)�y�c(��)�v�Ƃ���Ă��܂��B
�����A���̒������ɂ͓V����̎x�������삪�������Ɨ���Ă��܂����A�����k���̌����ʕt�߂���́A�V�W�~��n�}�O���̉�����������A���Ă��̕ӂ��т͌��������Ƃ���������܂��B
�@

�@
�����R�Q�i�P�W�X�X�j�N�A�R�R�V�˂̓ԓc�������A���Č����̊J��͎n�܂�܂����B
�������̂�����͒��ł��Â������̌����тŕ����A�J��҂����͓D�Y���E�S�y���̓y�ƌ����������A���ǂ𑱂��铬���̓��X�𑗂������Ƃ��A���̎����Ƃ��Ďc���Ă��܂��B
�@
����������l�̉i����J�̂����������āA�u���n�̒��v�ƌĂꂽ�������₪�ĉ��₩�Ȕ_���n�тւƕϖe���A���W���Ă����܂����B
�@
�ߑa���̐i�ޒ������C�Â������ƁA�E��̈Ⴄ�u�Ⴂ��������B�v���W�܂��č�����u�G�{�̗��v�́A�m�I��Q�҂̎{�݁u�����w���v���x���ŁA���̏o�����u�����E��������Ă��n�̉�v�����܂�܂����B
�@
���݂ł́A���R�Ȍ�����̗���ɊJ���ꂽ�c�Ɣ��A�����Ă��̔w�i�ɍL����ɂ₩�ȋu�ƎR�т̒i�u�n�т��A���[���b�p�̓c�ɂƂ��������i��D�萬���āA�K���l�X�̖ڂ��y���܂��Ă���܂��B
�@
�@
���@�u�����E��������Ă��n�̉�v�̖�
��������Ă�_�Ɓ@������Ɍւ��_�Ƃ��I
�u�����E��������Ă��n�̉�v�͕����Q�N�ɐݗ��B
���S�E���S�Ȕ_�Y���Ƃ��ėL�@�͔|�E���ʍ͔|�̐��Y�y�є̔�������i�߂ĂQ�O�N���z���܂����B
�@
���@�킽�������̖�̍���
���@�����܂͎g�p���܂���B
���@�엀�ȕޏ���v��I�Ɋg�債�܂�
���@�֍����{�ɑ͉X��E�Δ�E�L�@�엿���{�p���܂��B
���@�y�땪�͂�����Ń~�l�����̃o�����X�����܂��B
�@
���@�킽�������̖��_��Ƃ�
���@�S���f������50���ȏオ�L�@�엿����їL�@���ł��邱�ƁB
���@�����g�p��2�N�ȏコ��Ă��Ȃ��c���ł��B
���@���w�_��U�z�͂����������Ă���܂���B
���@�_���֎��ނ��g�p���Ă���܂��B
���@����13�N���k�C���L�@�_�ƌ������c��̔F�܂����B
(���_��E�����w�엿�͔|�_�Y��)
�@
���@�킽�������̌��_��Ƃ�
�� �����܂͌����I�Ɏg�p���܂���B
���@�_��͐����ɉe���̏��Ȃ����̂��Œ�Z�x�Ŏg�p���Ă��܂��B
(�͓��n�ʏ�͔|4�`5����x��5���ȉ��ōs���܂��B)
���_��ɂ��Ă͎g�p�������̂�`���Ƃ��܂��B
���_��ɂ��Ă͎g�p�������̂�`���Ƃ��܂��B
�@
�@
�����E��������Ă��n�̉�
������ӏ�
�@
�������̐g�̉��́A���܂��܂ȉ��w�����ɂ���ĉ�������A���܂�n���K�͂Ŋ��������i�s�����E�I�Ȗ��ƂȂ��Ă��܂��B
�����āA�������̐H���́A���Y�i�K�ƗA���ۊǒi�K�ɂ�����_��̎g�p�A���H�i�K�ɂ�����H�i�Y�����̎g�p�Ȃǂɂ���ĉ��w���������̗��p�x�͈ˑR�Ƃ��Č������Ă���܂���B
�@
���������̂��ƂŁA����҂��A�u�H�̈��S�v��g�߂Ȗ��Ƃ��ċ����S�������A�ߏ�Ȃ܂łɔ_����g�p����_�ƂƁA���H�i�ɑ���e��̐H�i�Y�����̎g�p���d��Ȏ��Ԃɂ���Ƃ��Ă���̂́A���w���������̊댯���ɑ���[���F���̌���ł���A���̂��Ƃ��炵�āA�g�̂̌��N�ƐH�̈��S�Ɋւ������҂̖��ӎ��̍��܂�͓��R�ł��B
�@
�������_���́A�u�H�͐����v�ł���Ƃ����F���ɗ����A����҂����߂���S�Ȕ_�Y���Ƃ��̉��H�i�Y���������ׂ��ł���Ƃ������o�Ɋ�Â��āA�u����Ɍւ肤��v���S�Ȕ_�Y���Y���Ă������Ƃ�����̂ł��B
�@
���̂��Ƃ��炵�āA����������́A�_�ƂƔ_���̎Љ�I�ӔC�̗��ꂩ��A�_�Ƃ̊�{�ɗ����Ԃ�A���̒n���̐��Ԍn�����������u�y���v���d��ȉۑ�Ƃ��āA���w�엿�Ɣ_��Ɉˑ����Ȃ��_�@�����H���Ȃ���Ȃ�܂���B
�@
���S�ȓy�ƗL�@�E���_��_�@����ѐ����Ȕ_�ƋZ�p�ɂ���Đ��Y���ꂽ�_�Y���ƐH�i�́A���ꎩ�̕t�����l��������ł��B
�@
�{��́A�����Q�N�Ɂw�H�͐����Ȃ�x�Ƃ����F���Őݗ����A���w�엿�Ɣ_��Ɉˑ����Ȃ��ŁA���Ԍn�������_�Ƃ��s���A����҂̊��҂ɉ�����ׂ��w�͂��Ă��܂������A���܂������̏�Ԃɂ���܂��B�����ɂ����āA�w�H�͐����Ȃ�x��b�ɂ��āw�_�͐H�̖��x�w�_�͐�����́x�w�����_�ɑ������x��M�O�Ƃ���簐i���܂��B
�@
����������́w�����x�Ƃ������Ƃ��L���[�����������F�����āA����҂̐^���ȗv���ɂ������邱�ƂɂƂ߂�ƂƂ��ɁA�^�ɕ����I�ɖL���Ŗ��邢�_�ƂƔ_����z���Ă����܂��B
�@
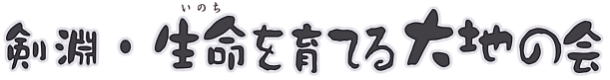
�@
�������̏Z�ޒ��u�����v(����Ԃ�)�͖k�C���k���̖~�n�̒��ɂ��钬�ł��B
�N�ԉ��x�����T�O���ȏ゠��A���n���́u���t���v�ɓK���������̉��x����L���܂��B
�J�����A�D�Y���E�S�y���̓y�ƌ������������x���y�n�́u���ǁv���s���Ă��܂����B
�@
�ߔN�܂ŁA����E���ʂ̉��w�엿��_������݂܂������A������u�������͐H�ׂ���̂Y���Ă���v���ƂɐU��Ԃ�u�H�ו��͐l�̐���(���̂�)�̂��Ɓv�ł��鎖���ēx�F�����A�L�@���E��������p�������_��͔|���n�߂邱�ƂŁu�H����v���ɗ������앨�A�������̌����u����(���̂�)�̂��Ɓv�����邱�Ƃ��l����ɗD�����A�X�ɂ́A�q���̖����̂��߂ł�����ƁA���݂͔̍|�@���n�߂邱�ƂƂȂ�܂����B
�@
�����͉ߑa�����i�ޏ����u�܂��v�ł��B
������A�u���������C�Â������v�E�E�E�����l���o�����܂��̐N�B���u�G�{�v�Əo��A �������u�G�{�̂܂��v�ɂ��悤�ƒ������E�Ƃ��ďW�܂�n�܂����G�{�̗��Â���B
���̏o���̒��Œm�I��Q�Ҏ{�݁u�����w���v�̐E���≀���ƒm�荇���A�������l�����Ƃ� �u�����E��������Ă��n�̉�v�����邫�������ƂȂ�܂����B
�@
���̉�����́A�x�O�́u�����w���v���ɋ��_��u���A�ޏ��ƁA�ב���A�������̋��͑̐��̊�A���т�ς� ����5�N�ɂ͂��X���[�Y�ȑΉ����ƒ����S���Ɏ��������\���Ă���܂��B
�܂��A���N��萼���w���߂��ɐV�݂��ꂽ�m�I��Q�Ҏ��Y�{�݁u�k�̓m�Ɂv�ɂ̓g�E�����R�V��W���[�X�̉��H���ϑ����Ă��� �A�����͂��A�������i������E����ɋ߁A���ǂ��u�������Ɓv�����͂��ł���悤�w�͂��Ă���܂��B
������ʂ��Ċw�т������Ƃ�����́A�����I�Ȕ_�Ǝ҂Ƃ��Ė����ւ̑f���炵����Y�Â����簐i�������Ǝv���܂��B
�@
�@
�����E��������Ă��n�̉�
�����̂��ƈꗗ�\
�@
���j�݁@�@�@�@�@�@8�����{�`�@�@�@�@�T���_�A�X�[�v�A䥂ł�����
�����[�N�C���@�@�@9����{�`�@�@�@�@�J���[�A�V�`���[�A�����Ⴊ��
����݁@�@�@�@�@�@9����{�`�@�@�@�@���ӂ������A�R���b�P�Ȃǂ�
���L�^�A�J���@�@�@9����{�`�@�@�@�@�R���b�P�Ƀ|�e�g�P�[�L��
�����肠����Z�@�@8�����{�`10�����{�@�@�@�@�z�R�z�R�E�z�N�z�N�A�k���̖�
���G���e���������w���@�@8�����{�`10�����{�@�@�@�@�܂�₩�ȊÖ�
���ቻ�ρ@�@�@�@12������@�@�@�@�@�����Ȃ�قǔ��������Ȃ�~������
���ʂ˂��@�@�@�@9�����{�`2�����{�@�@�@�@���ŐH�ׂ���قǓ����ȊÖ��B
���l�Q�i�y�t���j�@�@8�����{�`10�����{�@�@�@�x�[�^�J���`���������ς��I
���哤�A�����A�����A�Ƃ瓤�A���哤�@�@�@�@�@�@11�����{�`
���u�荕�哤�@�@�@�@�@�@�@�ʔN
���g�}�g�W���[�X�@�@�@�@�@�@�ʔN
���L�����b�g�L�b�X�@�@�@�@�@�@�ʔN
�������W���[�X�@�@�@�@�@�@�ʔN
���������i�n�����^�J�j�@�@�@�@9�����{
�������@�@�@�@�@�@9�����{
�����_��[���@�@�@�@�ʔN
���t�����N�t���g�@�@�@�@�ʔN
�@
�@

�ΐ쌧�F��
�L�@�_�Y���������ƎҐΐ쌧�F��ԍ��@No.1001