「トマトが赤くなると医者が青くなる」
医者いらずの薬効を持つ
緑黄色野菜の女王・トマト
抗がん作用・動脈硬化の予防
老化の抑制・風邪感染症の予防
京阪神地区でも美味しさで評判の
石川のトマト
●小松市のトマト 5月上旬から
●白山市のトマト 5月中旬から
●能登の海洋深層水トマト 6月上旬から
 |
●小松市のトマト
小松市は北陸最大のトマト産地です。
小松のトマトには、生産者の「赤い情熱」がたっぷり。
「実がしっかりしていて甘味がある」と好評です。
環境にやさしく安心しておいしいトマトを食べてもらおうと「マルハナバチ」を使った自然受粉でホルモン剤の使用を減らしています。
また「もみがら養液栽培」で土壌消毒剤などを減らした低農薬栽培。
トマト生産者の奥さんたちの意見を基に、小松産のトマトで作ったトマトカレーが商品開発されました。
水は一切使用しない、トマトの程よい酸味と野菜の旨みとコクを引き出し、癖になる美味しでなかなかの評判です。
●白山市のトマト
「消費者には食べて美味しく、生産者には作って楽しい、健康的な野菜を」。
減農薬減化学肥料栽培による「クリーントマト」生産です。
半促成トマト 5月中旬〜7月中旬
夏秋トマト 7月上旬〜9月下旬
抑制トマト 9月上旬〜11月下旬
土づくりについては、地域で生じる牛糞と籾殻を原料とする籾殻牛糞堆肥による土作りを徹底し、全窒素投入量の60%以上を有機物由来で対応しています。
化学合成農薬は極力使用しないようにしています。
また、防除回数も従来の平均9回から3回へと1/3程度に軽減しました。
平成13年には持続農業法に基づくエコファーマーとして認定されました
また、環境保全型農業推進コンクール大賞受賞しました。
●能登の海洋深層水トマト
能登半島の能登町では、海洋深層水をくみ上げる施設があり、水深320メートルの深さから、良質の深層水を組み上げています。
能登町では、この海洋深層水を使って育てたトマトがあります。
海洋深層水には、植物生育に必要な天然組成の微量成分や様々なミネラルがバランスよく含まれています。
また浸透圧を利用することでトマトの実に含まれる水分を調節し、甘くてずっしりとした実が出来上がるのだそう。
食べてみてびっくり! 糖度が8度から、中には10度近いトマトも。
ミネラル豊富な濃い味わいの能登海洋深層水トマトをぜひお味わいください

■ トマトの機能・効能
www.kagome.co.jp/tomato/tomato-univ/literature/index.html
1、トマトに含まれるリコピンとは?
トマトの赤い色素は「リコピン」という成分で、とりわけ「抗酸化作用」が強いことが分かっています。
「リコピン」は「カロテノイド」(動植物に含まれる、赤や黄色、オレンジ色の色素)のひとつで、「カロテノイド」には「リコピン」のほか「β-カロテン」などがあります。
「β-カロテン」はにんじんやパセリ、ほうれん草などに多く含まれ、体内でビタミンAに変化するため、早くから栄養学的に注目されていました。
しかし近年、「カロテノイド」自体が強い抗酸化作用を持つことが知られるようになり、急激に注目度がアップしました。
そして、「カロテノイド」の中でも、とりわけ「リコピン」は抗酸化作用が強く、その作用は「β-カロテン」の2倍以上、ビタミンEの100倍以上にもなることが分かったのです。
2、リコピンと生活習慣病に関する研究
いくつかの研究事例により、リコピンの抗酸化作用は疾病に対する予防効果があることが確認されています。
トマトの赤い色素「リコピン」には、様々な生活習慣病の原因となる活性酸素を消去するはたらき=「抗酸化作用」があります。
世界各地でリコピンに関する研究が行われているほか、カゴメ総合研究所も大学・研究機関と共同研究を行い、その効能を確認しています。
2006年 順天堂大医学部 瀬山先生らとの 共同研究
【トマト(リコピン)と肺気腫】
希釈したトマトジュースを老化促進モデルマウスに与え、タバコの煙による肺気腫への影響を評価したところ、有意に肺気腫の発生を抑制した。
希釈したトマトジュースを老化促進モデルマウスに与え、タバコの煙による肺気腫への影響を評価したところ、有意に肺気腫の発生を抑制した。
2004年 愛知医科大 伊藤先生らとの共同研究
【トマト(リコピン)とがん治療(放射線治療障害)】
リコピンを摂取させたマウスの腹部に放射線を照射し、組織障害に対しての影響を評価したところ、リコピン投与により組織の障害を有意に抑制し、放射線治療の副作用に対し防御的に働くことが期待された。
リコピンを摂取させたマウスの腹部に放射線を照射し、組織障害に対しての影響を評価したところ、リコピン投与により組織の障害を有意に抑制し、放射線治療の副作用に対し防御的に働くことが期待された。
2004年 昭和女子大学 木村先生らとの共同研究
【トマト(リコピン)と糖尿病】
トマトおよびオリーブオイルを使用したメニューが血糖値の上昇を抑制することをヒトで確認した。
トマトおよびオリーブオイルを使用したメニューが血糖値の上昇を抑制することをヒトで確認した。
2002年 東宇都宮病院 森先生らとの共同研究
【トマト(リコピン)と糖尿病】
リコピンを糖尿病モデルラットに与え、糖尿病の病状に対する影響を評価したところ、リコピンの投与により糖尿病の発症につながる耐糖能異常を改善することを確認した。
リコピンを糖尿病モデルラットに与え、糖尿病の病状に対する影響を評価したところ、リコピンの投与により糖尿病の発症につながる耐糖能異常を改善することを確認した。
2001年 近畿中国四国農業研究センター 関谷先生との共同研究
【トマト(リコピン)と肥満】
in vitro(細胞)での評価により、リコピンなどのカロテノイドが、前駆脂肪細胞から脂肪細胞(脂肪の蓄積を行なう細胞)への分化を調節することを確認した。
in vitro(細胞)での評価により、リコピンなどのカロテノイドが、前駆脂肪細胞から脂肪細胞(脂肪の蓄積を行なう細胞)への分化を調節することを確認した。
1998年 秋田大学 成澤先生らとの共同研究
【トマト(リコピン)とがん】
希釈したトマトジュースを発がん剤を与えたラットに継続的に与え、大腸がんの発症率を比較したところ、トマトジュースを飲んだラットは水を飲んだラットと比較して大腸がんの発症率が有意に減少した。
希釈したトマトジュースを発がん剤を与えたラットに継続的に与え、大腸がんの発症率を比較したところ、トマトジュースを飲んだラットは水を飲んだラットと比較して大腸がんの発症率が有意に減少した。
1996年 カゴメ単独
【トマト(リコピン)と動脈硬化(LDL酸化抑制)】
トマトジュースを長期飲用したヒトの血液(LDL)には、リコピンなどのカロテノイドを豊富に含んでおり、一重項酸素を発生させても過酸化物の産生が有意に遅かった。
トマトジュースを長期飲用したヒトの血液(LDL)には、リコピンなどのカロテノイドを豊富に含んでおり、一重項酸素を発生させても過酸化物の産生が有意に遅かった。
3、リコピンと美白・美肌の関する研究
「リコピン」は、生活習慣病の予防だけでなく、美白・美肌にも有効なことがカゴメの研究で明らかになってきました。
「リコピン」は、シミやソバカスなどの原因となる、紫外線によって生じるメラニンの生成を促進する活性酸素を消去するとともに、メラニンの生成に必要な酵素「チロシナーゼ」の働きを抑えます。その結果、美白につながるのです。
最近ではトマトの輪切りを顔などに貼る“トマトパック”や、お風呂の入浴剤代わりにトマトジュースを使う“トマト風呂”で直接効能を得ようとする人もいるようです。
しかしながら、皮膚にトマトをのせたりしても、リコピンはなかなか体内には取り込まれません。
それよりは、ジュースなどのトマト加工品を摂取する方が、確実に体内にリコピンを取り込むことができ、そして皮膚にも蓄積されます。
4、活性酸素の話
活性酸素とは、通常の酸素と比べてモノを酸化する力が強い酸素です。
普通に生活していても、体に入った酸素の2〜3%が活性酸素になるといわれます。
また、日光を浴びたり、激しい運動をしたときも活性酸素が増加します。
通常、活性酸素は体内に侵入した細菌などの異物を攻撃したり、体内の酵素反応を促したりするなど、私たちの生体にとって大切な役割を果たしています。
つまり活性酸素は、酸素を利用してエネルギー代謝を行う生物では必ず生成されるもので、本来体内に備わっている活性酸素消去機能が順調に働いていれば、問題視されるものではありません。
しかし、現在、活性酸素が大きな注目を集めているのは、精神的なストレスや喫煙、飲酒、排気ガス、紫外線、電磁波、放射線といった極めて現代的な生活要因で活性酸素が増加している背景があるからなのです。
体内の消去機能では処理しきれなくなった過剰な活性酸素が、その強い酸化作用によって、遺伝子(DNA)を傷つけたり、脂質や蛋白質を変性させます。
こうした流れから、活性酸素が、近年増加傾向にあるがんや脳卒中、心臓病などの生活習慣病の原因になることが確実視されてきています。
5、リコピンの『活性酸素消去力』
「リコピン」をはじめとする「カロテノイド」は一般に、活性酸素の中でも、特に「一重項酸素(いちじゅうこうさんそ)」と呼ばれるものに対する消去能力が高いことが知られています。
安定した形で存在する通常の酸素を「三重項酸素(さんじゅうこうさんそ)」といいます。
これが、何らかの原因で不安定な形になったものが「一重項酸素(いちじゅうこうさんそ)」です。
「一重項酸素」は、活性酸素のひとつで、安定した「三重項酸素」と比較して高いエネルギーを持っています。
「一重項酸素」を消去するには、もともと安定した形だった「三重項酸素」に変換する方法と、自身を分解する方法があります。
「カロテノイド」は前者の作用が、ビタミンEは後者の作用が強いことが分かっています。
「活性酸素(一重項酸素)消去能力」を、他の天然の抗酸化物質と比較すると、リコピンの強さが分かります(下表参照)。
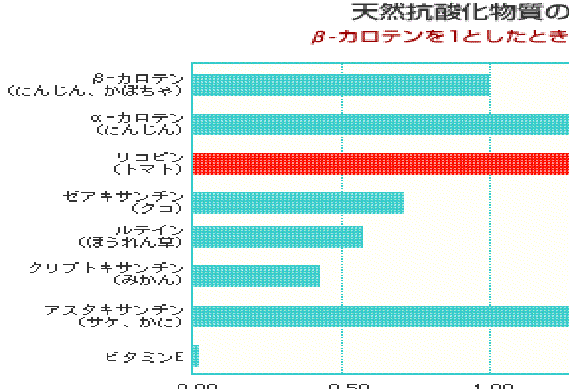
6、ライフステージ別リコピン効果
●胎児・幼児〜赤ちゃんがはじめて出会う「酵素」
赤ちゃんは、誕生して初めて肺呼吸を始めるその瞬間から、空気中の酸素を利用します。
しかし同時に、酸素の害にも初めてさらされます。
その害のことを「酸化ストレス」と呼んでおり、抵抗力が未熟なままの新生児・乳児にとっては、この「酸化ストレス」と戦うためにも、「リコピン」などの抗酸化物質の存在が特に重要と考えられています。
カゴメ総合研究所では、トマトの摂取量が多い母体ほど、母乳や臍帯血中の「リコピン」含量が多くなることを確認しています。
●若年層〜「リコピンダイエット」
肥満は、様々な生活習慣病の危険因子とも言えますが、日本においてBMI(体格指数)が25以上の「肥満者」の割合は、30代から60代の男性ではいずれも30%以上であり、20年前に比べ約1.5倍に増加しています。
女性では、40代の17.2%、50代以上では24.9%以上が肥満者です(厚生労働省「平成13年国民栄養調査」による)。
肥満は、体にとって余分なエネルギーが脂肪として蓄積されることで起こります。
カゴメ総合研究所では、「リコピン」には「前駆脂肪細胞」が脂肪を蓄積する「脂肪細胞」に成長するのを抑制する働きがあることを、培養細胞を使った実験で確認しています。
「脂肪細胞」への成長を抑制することが、太りにくい体質につながっていくかもしれません。
●中年層〜血糖値をコントロール
日本人の成人の6人に1人は「糖尿病患者」か「糖尿病予備軍」と言われています(患者数:740万人、予備軍:880万人、合計1,620万人/厚生労働省「平成14年 糖尿病実態調査」による)。
「リコピン」には、体内でのインスリンの効き目が悪くなるのを防ぎ(インスリン抵抗性改善)、正常に血糖値を下げる働きを保持させる効果があることが分かりました。
また、トマトに含まれる「クエン酸」は、デンプンをブドウ糖に分解する酵素の活性を抑えるため、糖の吸収を抑制します。
●壮年層〜血管をきれいに
いわゆる「コレステロール高め(220mg/dl以上)」の人は、成人男性の26.4%、女性の33.1%にもなります(厚生労働省「平成13年 国民栄養調査」による)。
細胞膜の材料となるコレステロールは、人間にとって本来なくてはならない成分ですが、過剰な摂取によっていわゆる悪玉コレステロール(LDL)が増加し、その酸化が進んで血管壁に溜まると、動脈硬化が進行します。
「リコピン」は、悪玉コレステロール(LDL)の酸化を抑制し、動脈硬化を予防する作用があることが分かっています。
●高年層〜「リコピン」で痴呆対策
老化に伴う学習・記憶能力の低下は、脳の神経が酸化されて脱落してしまうことが一因です。
脳の神経細胞は、特に活性酸素に弱いのです。
動物を使った実験では、「リコピン」を摂取することにより、体内で発生した活性酸素が神経細胞を酸化・変性させようとするのを抑制し、その結果、老化に伴う学習・記憶能力の低下の遅延が確認されました。
7、リコピン吸収を抜群にする
●生活習慣病のガードマン、リコピン
トマトの鮮やかな「赤い色」には、カラダにうれしいパワーがギュッと詰まっています。
赤い色の正体はカロテノイドのひとつであるリコピンという色素。
カロテノイドとは動植物に含まれる、赤や黄色、オレンジ色の色素のこと。
そのカロテノイドのひとつで、にんじんやかぼちゃなどに多く含まれるβ-カロテンは、体内でビタミンAに変化することが知られていました。
しかし、カロテノイド自体はただの色素にすぎず、わたしたちの健康とは何の関係もないと思われていたのです。
ところが研究の結果、カロテノイドには「悪玉酸素」ともいわれる活性酸素を消し去ってくれる作用があることが、最近になってわかりました。
なかでもリコピンにはβ-カロテンの2倍以上の消去能力があることがわかり、おおいに注目を集めています。
かたよった食事や飲酒、また過度の運動などで体内の活性酸素が増えると、細胞が傷つけられてしまいます。
いってみれば、増えすぎた活性酸素が細胞にいたずらし、「体をサビたような状態」にしてしまうのです。
それがガン細胞のできる一因になったり、動脈硬化などの生活習慣病のきっかけになったりするといわれています。
リコピンはこの活性酸素を消し去って、生活習慣病から私たちの身体を守ってくれるガードマンのような働きをしているのです。
緑黄色野菜の中で、トマトにはこのリコピンが最も多く含まれています。
●効果的にとるために
では、どのようにすると効率よくリコピンをとることができるのでしょう?
リコピンには、もともと油に溶けやすい性質があります。
そのため油を使った調理法によって、吸収がぐんと高まります。
リコピンは熱に強いので、炒めたり煮込んだりしても成分がそれほど減少する心配もありません。
むしろ生で食べるよりもオリーブオイルなどと一緒にトマトソースにしたり、シチューのベースなどとして調理するほうが、より効率よくリコピンをとることができます。
もちろんトマトジュースやピューレー、ケチャップなどの加工品を利用するのもよい方法です。
イタリアには、トマトとオリーブオイルを使ったメニューが数多くあります。
イタリア料理は味だけではなく、実はガンや生活習慣病の予防の面でも非常に優れているのです。
女性におすすめのリコピンを効果的にとる手軽な方法は、朝食などにトマトジュースと牛乳を組みあわせてとることです。
牛乳の脂肪分によってリコピンの吸収が高まり、また女性に不足しがちなカルシウムもあわせて補うことができるからです。
牛乳をかけたシリアル&トマトジュースという組み合わせなら、忙しい朝にもぴったりです
■ トマトの歴史
www.kagome.co.jp/tomato/tomato-univ/literature/index.html
1、トマトの語源
●語源は「膨らむ果実」
トマトという呼び名は「膨らむ果実」を意味する「トマトゥル」からきています。
はるか昔、メキシコ湾をのぞむベラクルス地方のアステカ人がこう呼んだのが始まりです。
トマトゥルとは元来「ホオズキ」を指し、メキシコではホオズキを煮込んで料理に使っていたところから、形がよく似たトマトも同じ名前で呼ばれたようです。
ところで、この「トマト」という呼び名、世界共通だと思っている人も多いのでは?
実は、イタリアでは「ポモドーロ(黄金のリンゴ)」、フランスでは「ポム・ダムール(愛のリンゴ)」、イギリスでは「ラブ・アップル(愛のリンゴ)」と、さまざま。
なぜリンゴ?と思われるかもしれませんが、昔からヨーロッパでは値打ちの高い果物や野菜を「リンゴ」と呼ぶ習慣があったからのようです。
●黄金のように貴重な果実
トマトに関する世界最古の文献は、植物学者マッティオーリが1544年に出版した『博物誌』です。
また、イタリア語でトマトを意味する「ポモドーロ(pomodoro)」は、同じくマッティオーリが10年後の1554年に出版した改訂版の『博物誌』の中に初めて記載されています。
語尾のoroには、黄金や富のように貴重な物、あるいは金色という意味があるのですが、彼はトマトを「とても大切な物」という意味で表現したかったのかもしれません。
『博物誌』改訂版には「熟すると黄色になるものと赤色になるもの」と書かれていますから、彼が最初に見たトマトは黄金色、つまり黄色やオレンジ色の品種だったのかもしれません。
●リンゴから桃へ
トマトの学名は、ラテン語で「リコペルシコン・エスクレンタム」。
実は、この学名にもなかなか興味深い意味が隠されています。
リコペルシコン は「狼(lycos)」と「桃(persicon)」を合体させた言葉で、エスクレンタムは「食べられる」という意味。
すなわち「食べられる狼の桃」となります。
名付け親は、英国の植物学者フィリップ・ミラーで、1754年に発表しています。
「リンゴ」から「桃」に変わった経緯は定かではありませんが、「狼の桃」とは、いかにもたくましい生命力を感じさせるネーミングですね。
2、アンデス生まれのメキシコ育ち
●元祖はチェリータイプトマト
トマトの故郷は、南米ペルーを中心としたアンデス高原の太平洋側の地域という説がもっとも有力です。
さんさんと降り注ぐ太陽、カラリとした気候、昼夜の温度差、そして水はけのよい土壌・・・。こうした環境のなかで生まれたトマトの原種とは、いったいどんな形や味だったのでしょう?
植物学者たちの調査で、アンデス高原には8〜9種類の野生種トマトが自生していることがわかりました。いずれも現在のミニトマトに近い形で、たくさんの小さな実をつけたチェリータイプトマトです。
●メキシコへの旅
この野生種トマトは、人間や鳥によってメキシコに運ばれ、栽培され食用になったと考えられています。
中でも「ピンピネリフォリウム」は、糖度が高く、熟すと真っ赤になる野生のトマト。
これらを人間や鳥、獣が好んで食べ、種を排泄し、その種が発芽し、再び実を結ぶ。
そうして少しずつ分布を広げていき、やがてメキシコで食用として栽培されるようになったのです。
●220年前に北米へ
栽培トマトの発祥地・メキシコのお隣でありながら、アメリカにトマトが伝わったのは、ヨーロッパに遅れること200年余。
当時バージニア州知事だったトーマス・ジェファーソン(後の第3代大統領)が、1781年に自宅の庭で栽培を始めたという記録が残っています。
しかし農産物市場に並ぶほど本格的に栽培されだしたのは19世紀なかばになってからです。
3、トマトの大航海時代
●南米からはるかヨーロッパへ
メキシコで栽培されたトマトが、いつ、どのようにして海を渡りヨーロッパへ広がったのか?
これには1492年のコロンブスによる新大陸発見が大きく関係しています。
コロンブス以降、大勢のスペイン人が続々と新大陸に押し寄せ、その戦利品のひとつとしてトマトを持ち帰り、ヨーロッパに広めたと考えられています。
トマトに出会った最初のヨーロッパ人は、1521年にアステカ文明を征服したエルナン・コルテスという説が有力です。
●観賞用として栽培がスタート
ヨーロッパでトマトを食べるようになったのは18世紀になってからのことといわれています。
なぜ、トマトがヨーロッパに持ち込まれてから200年もの間、食用として受け入れられなかったのでしょうか?
その理由は強烈な匂いやあまりに鮮やかな赤い色への抵抗感、さらにナス科の植物には麻酔作用や幻覚作用のある植物が多かったことから、トマトも有毒植物であると信じられていたのでは、と考えられています。
一説によるとヨーロッパでトマトをはじめて栽培し食用としたイタリア人は、飢饉のためしかたがなくトマトを食べたといわれています。
3、トマトの日本デビュー
●江戸時代に渡来
日本にトマトが伝わったのは17世紀なかば。
徳川四代将軍・家綱のおかかえ絵師・狩野探幽が「唐なすび」と呼び、1668年にスケッチしています。
文献でもっとも古いものは、江戸前期の儒学者・貝原益軒の『大和本草』(1709年)で、「唐ガキ」と紹介されています。
最初はヨーロッパ同様、観賞用として珍重されていました。
食用になったのは明治以降。
キャベツやたまねぎ、アスパラガス、にんじんなどの西洋野菜とともにあらためてヨーロッパやアメリカから導入されたのでした。
●カゴメ創業者がトマトを栽培
その西洋野菜にいち早く目をつけ栽培に着手したのが、カゴメの創業者である蟹江一太郎。
兵役を終えて帰郷した翌1899(明治32)年の春のことです。
農家の跡取りだった一太郎は、愛知県知多郡荒尾村(現在の東海市荒尾町)の自宅の脇に、トマトをはじめさまざまな西洋野菜の種を蒔きました。
これがカゴメ誕生の第一歩です。
一太郎は、やがて収穫した西洋野菜の販売を始め、ホテルや西洋料理店など少しずつ得意先を増やしていきました。
しかしトマトだけは独特の青くささと、真っ赤な色が敬遠され、全く売れずに頭を悩ませます。
そんな折、西洋ではトマトを加工して使うこともあると聞き、舶来のトマトソースを手本に独自のトマトソースの開発に乗り出したのです。
●国産ケチャップの登場
蟹江家が一家総出で試作品に取り組んだ結果、1903(明治36)年に第1号のトマトソース(現在のトマトピューレー)が完成。
高い評価を受けるとともに事業規模も拡大。
5年後の1908年には、トマトケチャップとウスターソースの製造を開始しました。
当時はコロッケなどの洋食がもてはやされていたこともあり、トマトケチャップにさきがけてウスターソースが一気に大ヒット。
さらに大正初期から昭和にかけて、家庭料理の洋風化がすすむにつれ、トマトケチャップは大きく売り上げを伸ばし、私たちの家庭にもなじみの味として定着してきたのです。

石川県認定
有機農産物小分け業者石川県認定番号 No.1001