■ 野菜・果物と健康 (2)
■ 健全な食生活における野菜・果物の重要性 その2
野菜等健康食生活協議会事務局
財団法人食生活情報サービスセンター
■ 健全な食生活における
野菜・果物の重要性 (1)
野菜や果物が私たちの食生活に欠かすことができない食品群であることは、多くの方々がすでによくご存じのことと思います。
でも毎日どのくらい食べるのが望ましいのか、自分は望ましい量を食べているのか、なぜ野菜や果物を食べる必要があるのか、皆さんご存じでしょうか。
最初の囲みの数字は健康のために摂取するのが望ましい野菜、果物の1日当たりの目標量を示しています。
野菜では350g、果物では200gです。
ところが実際の摂取量は野菜では70gくらい少なく、果物では80gくらい少なくなっています。
実際の野菜摂取量では昨年より8g減っています。
果物はほとんど変化はありません。
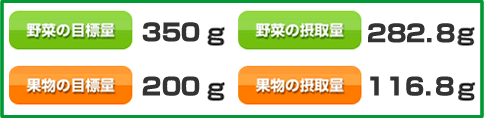
■ 野菜・果物の機能
1、ビタミンやミネラルの供給
2、カロリーや脂肪が少ないので、肥満予防につながる
3、様々な機能性成分を含んでいるので、各種疾病のリスクを低下させる
なぜ野菜や果物が重要かということになると、ちょっと分からないという方もいらっしゃるかもしれません。
上の2段目の囲みに簡単にまとめてみました。
メタボリックシンドロームや肥満が問題となる現代ですから、カロリーが低くそうな野菜は太らない食品かもしれないということは想像できる方は多いでしょう。
野菜はビタミンやミネラルが多いかもしれないと考える方がおられれば、いずれも正解です。
でも野菜の機能はそれだけではありません。
果物については、カロリーがあって、食べ過ぎると太ると恐れている人はいらっしゃいませんか。果物だけを大量に食べると問題かもしれませんが、りんご1つくらいは食べて頂きたいものです。
最近の研究では果物をたくさん食べる人は健康状態がいいという結果が多くの研究で発表されています。
1. 野菜・果物の栄養成分と消費実態
a. 日本人は野菜・果物をたっぷり食べているか?
日本人が1年間にどのくらい野菜や果物を消費しているかを農林水産省の食料需給表(1)のデータで、世代別の摂取量を厚生労働省の国民健康・栄養調査(2)のデータで見てみました。
食料需給表の消費量(供給純食料)は、毎年わが国の主要な農産物の生産量、輸入量、輸出量などに基づいて、国民1人が1年間に直接利用した量を示したものです。
キャベツの芯やみかんの皮など、廃棄される部分は含んでいません。
図1は野菜の消費量、図2は果物の消費量を示したものです。
野菜の消費量は徐々に減少しています。果物の消費量は横ばい傾向です。
図1 野菜消費量の推移(1人1年当たり[消費量 kg/年・人]
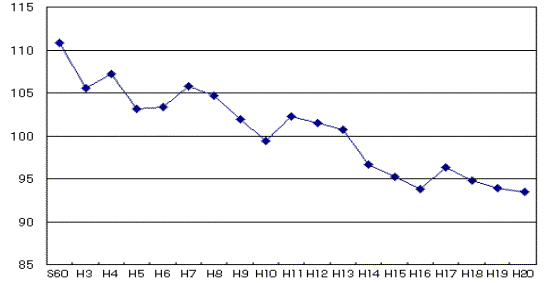
資料:「平成19年度食料需給表」(農林水産省)
図2 果実類消費量の推移(1人1年あたり)[消費量(kg/年・人)]
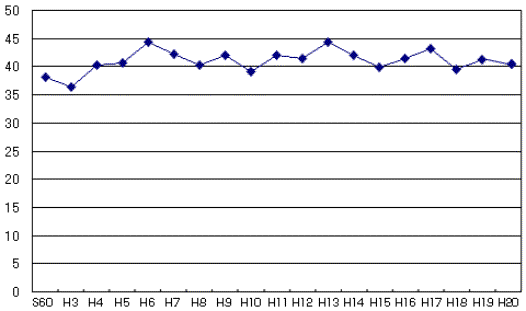
資料:「平成19年度食料需給表」(農林水産省)
図3と図4では世代別にみた野菜と果物の摂取量を比較してみました。
厚生労働省が例年11月のある1日に家庭の食事について15,000人くらいを対象として調査した結果です。
60歳代がもっとも野菜や果物を摂取していますが、若い世代の摂取量が低いことが目立っています。
20代や30代などでは目標量の7割、5割しか野菜、果物を食べていないのです。
60年代は日本人の健康を保つために重要と考えられている豆類(豆腐などの加工品も含む)、魚介類なども多く摂取しています。
もっともよい食生活をしているのは60歳代以上の日本人といえるでしょう。
図3 世代別にみた野菜摂取量(1人1日あたり)[g(グラム)]
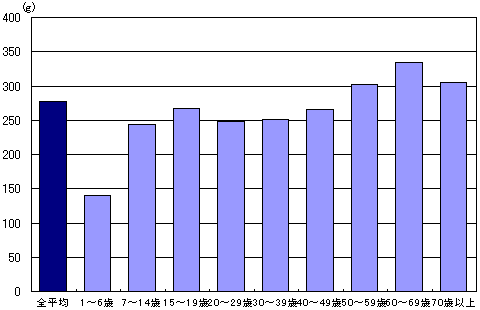
資料:「平成19年度国民健康・栄養調査報告」(厚生労働省)
図4 世代別にみた果物摂取量(1人1日あたり)[g(グラム)]
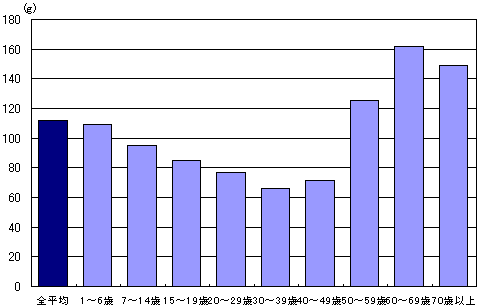
資料:「平成19年度国民健康・栄養調査報告」(厚生労働省)
b. 野菜・果物からどんな栄養素を摂取しているか。
野菜と果物から日本人がどの栄養素をどのくらい摂取しているかを図5と図6に示しました。
図5と図6では日本人が摂取している栄養素の平均摂取量を100%として、その何%を野菜と果物から摂取しているかを示しました。
野菜と果物両方からもっとも多く摂取している栄養素はビタミンA、ビタミンC、ビタミンK、葉酸、食物繊維です。
いずれも40%以上を占めていますから、野菜・果物の摂取が少ないと、これらは足りなくなる栄養素です。
その他にビタミンでは、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンEが20%前後、ミネラルではカルシウムと鉄が約20%です。
図5 野菜から摂取している栄養素量
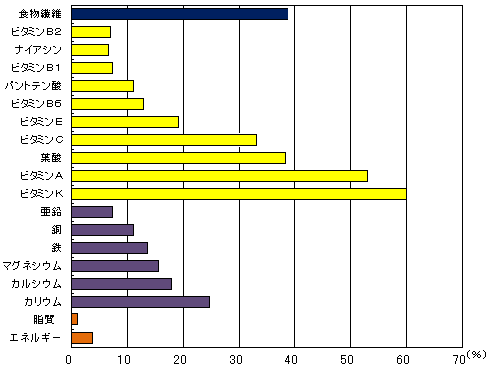
資料:「平成16年度国民健康・栄養調査報告」(厚生労働省)から計算
図6 果物から摂取している栄養素量
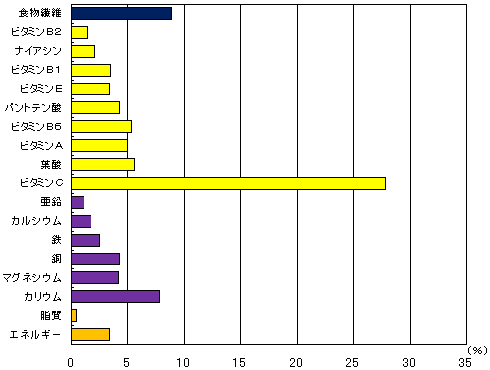
資料:「平成17年度国民健康・栄養調査報告」(厚生労働省)から計算
こうした微量栄養素といわれるビタミンやミネラルに比べると、野菜や果物にはエネルギーや脂質はごくわずかしか含まれていませんから、野菜・果物を多く摂ることでエネルギーや脂質の摂取を抑制するという役割もあるといえます。
このように、野菜・果物は栄養面で大変重要な役割を果たしています。
このため、我が国では野菜では1日に350g、果物では200gを食べる事を薦めています。でも、野菜350g、果物200gといわれても、どのくらいの量かピンとこない方が多いのではないでしょうか。
米国のファイブ・ア・デイ運動にならって、我が国でも分かりやすい摂取目安の提言が行われています。
、野菜では、小鉢や小皿に一盛りの野菜料理(調理前の生の可食部(食べる部分)の重さで70g程度)を1皿と数え、1日5皿〜7皿を目標に食べることを勧めています。
また、果物では、みかんのような小さなものは2個、りんごのような大きなものは1個を1日あたりの摂取目安としています。
そこで、野菜70gに含まれる栄養素の量を表1に、みかん1個に相当する100gの果物の栄養素量を表2として示しました。
(ここでいう果物100gは、皮などを含む重さで、可食部といわれる食べる部分のみの重さとしては75gとして計算しています。)
いずれも代表的な野菜や果物を選んでいますが、出典は5訂日本食品標準成分表です。