![]()
![]()
|
|
|
|
|

世界の8億4,000万人が食糧不足で苦しみ、実質的に飢餓人口が増えていることが、10月15日公表された国連食糧農業機関(FAO)の2002年版『世界食糧不安白書』でわかった【1998〜2000年の飢餓人口の平均】。
飢餓人工の95%以上は発展途上国。中国を除けば、国際基準年の1990〜1992年より5000万人増えた。飢餓人口の7割は農村に住んでおり、FAOでは農業・農村開発に力を入れるよう各国に呼びかけている。
白書によると、栄養不足の影響は、乳幼児に強く現われた。5歳未満の子どもは、年間に600万人死亡、うち300万人は栄養不足が原因だ。栄養不足に苦しむ国民が、人口の35%以上いる国での、新生児の平均寿命は38歳だ。
飢餓人口の数は増えたものの国の総人口に対する比率は20%から17%へと改善した。特に中国は、国際基準年に比べ、7400万人も飢餓人口を減らした。
逆に、中央アフリカ地域では栄養不足が悪化した。特に戦乱が続くコンゴ民主共和国では、飢餓人口の比率が32%から73%に倍増している。(10月16日付『日本農業新聞』より)

FOAは1996年にローマで行われた「世界食糧サミット」では、国連加盟国が2015年までに飢餓人口を半分にすることを目標として合意した。しかしながら、その目標達成に向けては、十分とはいえない状況にあり、目標達成に向けては、現行の減少ペースの10倍にあたる2400万人ずつ栄養不足を改善しなければならず、目標達成は厳しい状況だと述べています。
FOAの『世界食糧不安の現状2001』によると、大多数の発展途上国では、栄養不足人口が増加しています。
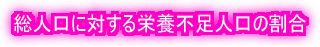
同書によると、開発途上国における1997年から99年における総人口に対する栄養不足人口の割合の甚だしいものを見ると、
| 割合 | 国名 |
| 70%以上 | ソマリア |
| 60%以上 | ブルンジ、コンゴ民主共和国の2カ国 |
| 50%以上 | アフガニスタン、エリトリア、ハイチ共和国、モザンビーク、アンゴラの5カ国 |
| 40%以上 | エチオピア、ザンビア、タンザニア、ケニア、中央アフリカ共和国、モンゴル、リベリア、シェラレオネ、ニジェール、マダガスカル、朝鮮人民共和国、ルワンダの12カ国 |
| 30%以上 | ジンバブエ、カンボジア、マラウイ、ギニア、チャド、イエメン、バングラディッシュ、ナミビア、コンゴの10カ国 |
| 20%以上 | ニカラグア、ラオス、ウガンダ、マリ、パプアニューギニア、カメルーン、レソト、ドミニカ、ブルキナファソ、セネガル、フィリピン、ボツワナ、スリランカ、インド、ネパール、ボビリア、グァテマラ、ホンジュラス、タイ、スーダン、ベネズエラの21カ国が挙げられています。 |

1990―92から1997―99年の間に大きく栄養不足人口が増大した上位10位の国は、コンゴ民主共和国が22%の増加、インドが24%の増加を初めタンザニア8%、朝鮮民主主義人民共和国とバングラデシュが夫々6%アフガニスタンとベネズエラが夫々4%、ウガンダ、ケニア、イラクが夫々3%の増加となっています。
栄養不足人口の増加は、中央アフリカ地域でもっとも多く、南アジア、東アフリカ、近東地域と続いています。
栄養不足人口が増加している国でのもっとも大きな要因は農業開発の遅れにあり、緊急の食糧援助と共に、地域内における自給体制拡充のために、農業部門の開発と技術援助こそが大切だと思われます。

過去30年にわたって、世界の食糧生産は、人口増加よりも速やかに成長しており、一人当りの利用可能な食料の量は、世界全体で1人1日当り2410カロリーから2800カロリーへ、また開発途上国だけで見ても全体で2110カロリーから2600カロリーに上昇しているといいます。
にもかかわらず8億人を超える栄養人口があることは、公平な食糧へのアクセスが伴っていないということです。
同じ感情を持つ人間として、同じ地球という村に生を受け、同じ時代を生きながら、富める人と貧しき人、飽食美食をほしいままにして肥満を気にして廃棄する人と、今日の食べ物にもこと欠き痩せ細っていく人がいる。好き放題を言って食べたいだけ食べ、糖尿病予備軍、成人病予備軍と言われている子どもと、着る服も履く靴もなく、暗がりの中で病魔に冒されても手当すら受けられず餓死する子供たちも少なくないと聞きます。
世界は、ごく一握りの人々によって富が収奪され、地球資源の大半が消費され、豊かな富める人たちの欲望によって地球環境汚染がされて行っています。
夏は涼しく冬は暖かい部屋の中で、当たり前のようにいただいている茶碗一杯のご飯をいただくにも、コップ一杯の水を飲むにも、いま同じ地球村の中で寒さや飢餓、病で苦しむ多くの同胞がすぐ隣にあることを忘れないようにしたいものです。
| |||||||||
![]()
![]()


