![]()
![]()
|
|
|
|
|
食品添加物について述べてきましたが、こうした添加物が使われている食品は避けた方がいいのではないか、と思われるいくつかの添加物について、西岡一氏の「すぐわかる添加物ガイド」からピックアップしてみていきたい。
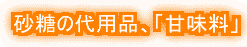
甘味料は、甘味をつけるためのものでそ、の代表が砂糖です。食品添加物の「甘味料」は、その砂糖の代用品として開発されたもので、甘味はつけますが、あくまでも代替品であって、食べものではなく“添加物”です。これにも化学的に合成された「人口甘味料」と、天然原料から作られた「化学合成品以外の甘味料」とがあります。
また、砂糖より甘味が強いのにカロリーの低い「高甘味度甘味料」と、砂糖より多少甘味は低いが、砂糖にはない機能(虫歯予防など)を持っている「低甘味度甘味料」があります。
現在、食品添加物の「甘味料」には、人口甘味料が4品目、天然系が22品目あります。
合成甘味料は、砂糖と同じ甘味を作り出すのに、価格は数百分の1で済みます。そもそも、合成甘味料がいっせいに使われだしたのは、加工食品時代に入ってからで、漬物からお菓子まであらゆる食品に使われました。これほど食品の大量生産にとって、ウマミのある話はなかったわけです。
砂糖の摂りすぎも有害ですが、砂糖の場合は使用量を少なめに抑えればほとんどの問題は解決しますが、添加物の甘味料は、産業の利益拡大のためでしか過ぎません。
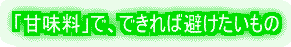
| [アスパルテーム] 人工甘味料 |
清涼飲料水、乳飲料、菓子類、漬物、アイスクリーム、氷菓、ガム、ダイエット甘味料などに、砂糖の代わりに甘味料として使われます。日本では、味の素が早くから輸出用として作ってきましたが、その安全性をめぐっては常に論議されてきました。動物実験ではエサに混ぜて与えると脳などに腫瘍が。低コストで砂糖の180〜200倍も甘い。 |
| [サッカリン] [サッカリンナトリウム] 人工甘味料 |
サッカリンはチューインガムのみに使われます。サッカリンナトリウムの主な使用食品は多く、清涼飲料、乳酸飲料、発酵乳、冷菓、各種菓子類、ジャム、魚肉練り製品、佃煮、煮豆、漬物、缶詰、ビン詰、ソース、ダイエット甘味料などの幅広い加工食品に用いられます。動物実験で染色体異常、子宮ガン、膀胱ガン、脊髄反射機能障害、運動麻痺、出血性胃炎、など多種多様の毒性が報告されています。国際ガン機関では、人に対して発ガン性を示す可能性がかなり高い、としている。甘味は砂糖の500倍で価格は数百分の1だといいます。 |
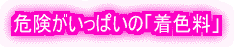
現在、日本で許可されている合成着色料には、タール色素と呼ばれる12種と、天然由来の合成色素7種がありますが、この中にどれ一つとして不安のないものはないとされています。
ことにタール色素は、ほとんどに発ガン性の恐れがあり、12種中8種は、既に発ガン性が確認されていて、諸外国では使用が許可されないことが多い物質です。タール色素はかつて、24種も使われていたことがありますが、それが次々と発がん性などの理由で禁止されました。タール色素の12種は何種類か混ぜて使われるもので、赤、黄、青、緑の4色を配合してどんな色でも作り出せるわけです。たとえば紫色には最低3種、コーヒー色やチョコレート色には4〜5種類が使われます。
一方、天然由来の着色料といっても、化学的に安全性が証明されたものではありません。自然系の原料とはいえ、昆虫や細菌など非食品が素材になっているものが多いのです。また、天然由来といっても、抽出から精製まで、工場で化学的に生産されます。この天然物の着色料添加物は、87種98品目にものぼります。そしてこれらの90%は輸入品です。
着色料は、食品衛生法で「食品を美化し、魅力を増すもの」と定義されています。食べものに人工化学物質を加えて見かけをよくする、というゴマカシが堂々と公的に認められているわけです。
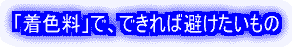
| [黄色5号] 合成着色料 |
菓子や清涼飲料水、農産加工品の着色に使われます。動物実験で乳腺ガンや染色体異常、また体重減少が認められ、アレルギー性があるとの報告もある。他のタール色素と同様に発ガン性の疑いが濃い着色料です。 |
| [黄色4号] 合成着色料 |
漬物、練りウニ、佃煮、ドロップ、あめ、和洋菓子、冷菓、飲料などの着色に使われます。発ガン性、染色体異常への不安、アレルギー性物質等の報告があり、食用色素中、最も幅広く多く使われる着色料です。 |
| [青色1号] 合成着色料 |
氷菓、菓子類、清涼飲料水、洋酒などの着色に使われます。発ガン性が疑われ、EC諸国では使用禁止となっています。 |
| [青色2号] 合成着色料 |
和菓子、焼菓子、あん類、冷菓などの着色に使われます。ラットで発ガンが見られ、染色体異常を引き起こすとの報告もあります。 |
| [赤色3号] 合成着色料 |
焼菓子、和菓子、洋菓子、かまぼこの他、福神漬けやサクランボなどの農水産加工食品などの着色に使われます。ラットの実験で赤血球数の減少、ヘモグロビン値の低下、成長抑制などが見られたほか、染色体異常や発ガン性への疑いがあります。ドイツ、ポーランドなどでは使用禁止の物質です。 |
| [赤色2号] 合成着色料 |
菓子、清涼飲料、冷菓、洋酒などの着色に使われます。ラット、ウサギによる実験で、肝臓にガンが発生。死産の増加、体重減少。遺伝毒性があり、染色体異常の報告もある。アメリカでは発ガン物質として使用禁止となっています。 |
| [赤色40号] 合成着色料 |
キャンディ、チューインガム、アイスクリーム、ジャム、清涼飲料水、アルコール飲料などの着色に使われます。アレルギーを引き起こす恐れがあるといわれます。 |
| [赤色105号] 合成着色料 |
かまぼこ、ソーセージ、でんぷ、和洋焼菓子などの着色に使われます。動物実験で遺伝子損傷性、遺伝毒性、染色体異常が認められ、また発ガン性が認められ、諸外国では使用が禁止されています。 |
| [赤色102号] 合成着色料 |
漬物、たら子、ソーセージ、つくだ煮、ジャム、飲料、和菓子、焼菓子、あめなどの着色に使われます。ラットの実験で、ヘモグロビン値の低下、赤血球数の減少、その他の症状が認められ、アレルギー性があり、染色体異常の疑いもいわれています。アメリカ・カナダ・ベルギーなどでは使用禁止です。 |
| [赤色104号] 合成着色料 |
かまぼこ、ソーセージ、でんぷ、和洋焼菓子などの着色に使われます。遺伝子損傷性、遺伝毒性、染色体異常が認められており、発ガン性の疑いが濃厚で外国では使用が禁止になっています。 |
| [赤色106号] 合成着色料 |
でんぷ、福神漬け、みそ漬け、桜えび、ハム、ソーセージ、和洋菓子などの着色に使われます。遺伝子損傷性、遺伝毒性、染色体異常が認められ、また発ガン性があるため、外国では使用が禁止になっています。 |
| [緑色3号] 合成着色料 |
菓子、清涼飲料などの着色に使われます。発ガン性、染色体異常の疑いがあり、アメリカ・EC諸国では使用が禁止されています。 |

「保存料」は食品中の微生物の発育や増殖を抑制して、「腐敗」を遅らせるための添加物ですから、強力に抑え込んでいても、いずれ時間が経てば食品は腐敗します。
これに対して、細菌を殺してしまうのが「殺菌剤」で、強い毒性があります。一般に食品は製造の初期段階で殺菌剤を使い、製造の後半で最終商品に残って有効に働くように、「保存料」を使います。これで本来の「防腐剤」効果が発揮されるわけです。
「保存料」は原理的には、冷凍・冷蔵、塩、酢・砂糖漬け、燻製、ビン詰といった保存方法と並ぶものなのですが、それを化学薬品の力で強引に、はるかに強力にやってしまうところが、本質的に違います。
「保存料」が微生物の増殖を抑制できるのは、自らが化学物質として持っている細胞毒性を、微生物に働かせているからです。ということは、私たち人間の体の細胞や体内の有用微生物群に対しても、当然毒性を持っているということです。
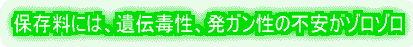
現在、保存料には、合成品6種、合成品以外で8品目が指定されていますが、合成品以外の保存料の安全性については殆んど不明だということです。
合成保存料のほとんどの物質に遺伝毒性の疑いがあるだけでなく、ソルビン酸と安息香酸エステル類には、発色剤の亜硝酸ナトリウムと反応して、発ガン物質を生成することも知られています。
「保存料」の実態は、食品産業にとって、大量生産と流通過程の拡大が要求する必然的な「長期保存」を目的とする添加物です。
この添加物も、食品生産者と販売業者の利益を安定確保させるためだけのものであって、それ以外の何ものでもないといえます。したがって、食品産業の利益にとってのみ必要不可欠の物であって、消費者にとっては、何のメリットもないどころか、常に危険なリスクを負わされているだけなのです。
本来、適正な生産量と適正な流通、そうして徹底した衛生管理の中で清潔に食品が作られていたならば、殺菌剤にしろ保存料にしろ、使う必要のないものなのです。私たちには、自然の摂理に反して作られた、腐らない食品を拒否するくらいの感覚が必要なのです。

| [亜硫酸塩] 合成保存料 |
「亜硝酸塩」には、保存料としての効果の外に、「酸化防止剤」としての効果、「漂白剤」としての効果があります。主な使用食品は、かんぴょう、干しブドウを除く乾燥果実、コンニャク粉、ゼラチン、果実酒、雑酒、チェリー砂糖漬け類、水あめ、天然果汁、甘納豆、煮豆、エビむきみ、冷凍イカ剥き身、などの多種があります。ラットによる実験では、多発性神経炎、骨髄の萎縮、催奇形性、代謝障害などが見られ、遺伝毒性が認められた、との報告があります。 |
| [安息香酸] [安息香酸ナトリウム] 合成保存料 |
キャビア、マーガリン、清涼飲料、シロップ、しょうゆ、の食品に限って使用が認められています。ラットに与えて、過敏状態・尿失禁・けいれんが生じ、犬では、運動失調・てんかん様けいれんなど急性毒性が見られ、遺伝毒性の報告もあります。 |
| [ソルビン酸] [ソルビン酸K] 合成保存料 |
魚肉練り製品、食肉製品、魚介乾燥品、漬け物類、つくだ煮、ウニ、みそ、燻製、ジャム、ケチャップ、乳酸飲料、など広範な食品に使われます。動物実験で肝の重量増加、肝臓肥大、成長抑制、肝・腎・精巣の重量減少。また、ハム・ソーセージなどの発色剤に使われる亜硝酸ナトリウムと結合すると発ガン物質に変わる危険性があります。 |
| [パラオキシ安息香酸] 合成保存料 |
しょうゆ・果実ソース・酢・清涼飲料・シロップ・果実及び果菜の表皮、に限って使用が認められています。動物実験では胃炎、肝硬変の発生が見られ、染色体異常の報告があります。また、亜硝酸ナトリウムと紫外線下で反応して、突然変異誘発作用がある物質を作り出します。 |
| [プロピオン酸] [プロピオン酸カルシウム] [プロピオン酸ナトリウム] 合成保存料 |
チーズ、パン、洋菓子。以上に限って使用が認められています。目や皮膚、粘膜を刺激します。 |

用途名が「増粘剤」、「安定剤」、「ゲル化剤」、「糊料」といろいろある中から、製造者がもっとも適切と思う使用目的を選んで表示します。一般には、糊料あるいは増粘安定剤などと書かれます。
これらの用途は、従来は「糊料」と一括して呼ばれていたもので、多くはアイスクリームやソース類にある、トロッとしたノリのような感じを出すために使われています。これらの添加物の基本的な効果は、①粘稠性を出して食品の組織を形成。②油脂の乳化の安定と均一性。③ゼリーのような食品のゲル状組織形成。④食品のボディ感形成。⑤粘着性、被膜性、起泡性、保湿性などです。
これらの用途には、化学合成品が8品目。合成品以外のものが48品目指定されています。合成品以外の物が多く使われる傾向にありますが、バイオ技術を利用したものなど、いずれも直接食用とならないものが原料です。しかも原料も製品も、すべて輸入品です。
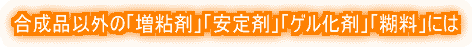
| [種子多糖類] | グァーガム、タマリンドガムなどがあり、ソースやタレ、漬物などの増粘剤、アイスクリームの安定剤として使用されます。他の添加物との併用が多い。 |
| [樹脂多糖類] | アラビアガム、ガディガムなどがあり、ドレッシングや調合香料などの乳化安定に使われます。 |
| [海藻多糖類] | アルギン酸、カラギーナンなどがあり、アルギン酸はラーメンの腰出しに、カラギーナンはゼリーなどのデザート原料に。 |
| [発酵多糖類] | キサンタンガム、カードラン、プルランなどがあり、キサンタンガムは種子多糖類との併用でソースやアイスクリームに使われます。カードランはゼリー化に、プルランはフィルム形成に使われます。 |
| [植物抽出物] | ジャムやゼリーに使われるペクチンが代表的物質です。 |
| [甲殻抽出物] | キチン、キトサン、グルコサミンなどがあり、カニの甲から抽出された添加物です。 これらはいくつかの物質が併用されることが多く「増粘多糖類」と表示されることも多い。 合成品、合成品以外を問わず、これらの添加物はやはり、食品製造の手間を省き、経費を安くあげる大量生産のための薬品であることにほかなりません。 |
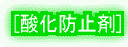
加工食品の油脂成分や、添加された色素は、時間の経過とともに酸素や光によって、変質したり変色したりします。これらの現象を酸敗といいますが、酸敗は食品の風味を損ねるだけでなく、有害な物質も生成させます。現代の食品産業と流通にとって、保存性は必須となっていますから、色素が添加されたり、油脂成分を含む加工食品には、酸化を防止するための酸化防止剤が使われています。
酸化防止剤には、合成品が18品目指定されており、合成品以外では36種43品目が指定されています。
酸化防止剤は単独で使うよりも2種以上を混合して使う方と効果があることから、1食品中に多種の酸化防止剤が使われることがある。発がん性や遺伝毒性が確認されている合成品もあり、これらが併用されることは相乗作用を含めた未知の危険性があります。
真空包装や低温保存などで酸化防止剤を使わない工夫もされていますが、長期保存を前提とした大量生産と流通経路のシステムを変更しないかぎり、酸化防止剤の使用はなくなりません。

| [亜硫酸塩] 合成酸化防止剤 |
食品中の油脂成分が酸化して変質するのを防ぐために使われます。合成保存料の中でも述べましたが、「亜硫酸塩」には、「酸化防止剤」としての効果の外に、「保存料」としての効果、「漂白剤」としての効果があります。主な使用食品は、かんぴょう、干しブドウを除く乾燥果実、コンニャク粉、ゼラチン、果実酒、雑酒、チェリー砂糖漬け類、水あめ、天然果汁、甘納豆、煮豆、エビ剥き身、冷凍イカ剥き身、などの多種があります。ラットでは多発性神経炎、骨髄の萎縮、催奇形性、代謝障害などが見られ、遺伝毒性が認められたとの報告があります。 |
| [EDTA-Ca・Na] [EDTA-Na] 合成酸化防止材 |
食品の酸化による変色や白濁を防ぎ、味を保存し腐敗を防ぐために使われます。缶詰とビン詰に限り使われます。遺伝毒性や催奇形性が報告されており、また、カルシウムを体外へ排泄させる作用があるため、カルシウム不足を招く恐れがあります。子どもの好む清涼飲料にも使われます。催奇形性の恐れがあるので妊婦は特に要注意です。 |
| [BHA] 合成酸化防止剤 |
パーム原料油、パーム核原料油に限って使用が認められているもので、発ガン性が確認され、対象品目がパーム原料油とパーム核原料油に制限されました。パーム原料油、パーム核原料油は、一般消費者が直接購入する食品ではありませんが、パーム油は菓子類やインスタント食品などさまざまな食品に使われ、ことに輸入商品に使われていることがある。 |
| [BHT] 合成酸化防止剤 |
油脂、バター、魚介冷凍品、鯨冷凍品、ガム、魚介乾燥品、乾燥裏ごし芋、に限って使用が認められています。動物実験で、血中コレステロールの上昇やヘモグロビンの減少とともに、肝臓・腎蔵にさまざまな異変・障害が生じています。遺伝毒性が認められ、ホルモン併用では発ガン性の疑いももたれています。またBHTは脂肪組織に蓄積する傾向があり、これを使った食品をとる際の食事内容に油分が多くなるほど危険性を増す可能性があといわれます。 |
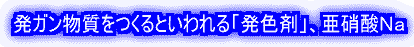
全ての添加物の中から“ワースト10”を選ぶとしたら、発色剤の「亜硝酸ナトリウム」は、その上位にくるだろうといわれています。亜硝酸ナトリウムは、それ自体の生理毒性もさることながら、最大の理由は、他の物質と反応して「発ガン物質ニトロソ化合物」をつくることです。このニトロソ化業物は発ガン物質の中でももっとも危険視されているものです。
発色剤が着色料と異なる点はそれ事態に色がないことです。発色剤の原理は、無色でありながら、食品中の成分と反応して、安定した色素を生じさせたり、色を固定したりする所にあります。
現在指定されている添加物3品目「亜硝酸ナトリウム、硝酸カリウム」「硝酸ナトリウム」は全て食肉用です。食肉類の色素は、肉や血に含まれるミオグロビン、ヘモグロビンなどの赤色色素ですが、これらは空気に触れたり加熱されたりすると、酸化してメトミオグロビン、メトヘモグロビンといった、褐色の色素に変化してしまいます。
ところが、発色剤の亜硝酸ナトリウムを添加すると、元のミオグロビンやヘモグロビンは、酸化しにくいニトロソミオグロビン、ニトロソヘモグロビンに変化します。これで、いつまでも鮮やかな肉色が保たれるという仕掛けです。
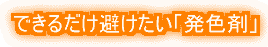
● [亜硝酸ナトリウム][硝酸カリウム][硝酸ナトリウム]合成発色剤――食肉や水産品の赤い肉色を保つために使われ、主な使用食品は、食肉ハム・ソーセージ、ベーコン、コンビーフ、魚肉ハム、イクラ、スジコなどです。遺伝毒性、催奇形成、発ガン性、アレルギー性も確認されており、市販の食品中からも、亜硝酸ナトリウムが天然の二級アミンと反応してつくる、強い発ガン物質「ニトロソアミン」が検出されています。米国では、ベビー食品への使用を全面禁止しています。亜硝酸ナトリウムが発ガン物質をつくる機会は次のような場合です。
| ① 魚に含まれる天然成分(ジメチルアミン=スジコやタラコには特に含有量が多い)と食品中で一緒になり、最悪の発ガン物質・ニトロソアミンに変わる。この発ガン物質は、ごく微量でネズミに肝臓ガンを発生させている。この反応は胃の内部と同じpH2〜3でいっそう良く反応し、単に亜硝酸ナトリウムを使った魚肉ハムや魚卵製品が危険なだけでなく、亜硝酸ナトリウム添加の食肉製品と魚を食べ合わせた時も、同様の危険があることを意味しています。ニトロソアミンは胃などから吸収されるので胃ガンの原因にもなる恐れがあるといわれます。また、この発ガン物質は胎盤通過性が高く、容易に母体から胎児に達し、新生児ガンの原因としても注目されています。 ② 肉のスジ部分に多く含まれている、プロリンと呼ばれているアミノ酸と反応して、発ガン疑惑物質をつくる。この反応は180〜200度で起こり、この温度は、ちょうどベーコンやソーセージを焼く温度です。 ③ 保存料のソルビン酸(食肉製品をはじめ多くの食品に使われている)と一緒に、酸性状態で加熱すると、いくつかの発ガン物質ができる。 ④ 保存料のパラオキシ安息香酸(しょうゆ、ソース、酢、清涼飲料などに使われている)と、紫外線下で反応して、突然変異を引き起こす発ガン疑惑物質をつくる。 ⑤ 酸化防止剤のBHT(魚介の冷凍品・乾燥品・塩蔵品、油脂、バター、乾燥うらごし芋などに使われている)と紫外線下で反応して、生理毒性の強い物質をつくる。 |
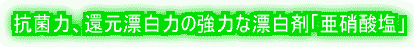
漂白剤は、薬品の還元作用を応用して食品中の有色成分を変化させ、白色または無色にする「還元漂白剤」です。この漂白剤には抗菌性や酸化防止効果もあるので、「保存料」および「酸化防止剤」としても指定されており、用途名は使用目的に応じて、製造者が選択することになっています。
還元漂白剤は、還元剤が食品中からなくなれば、また元の色に戻ってしまいます。食品が酸化によって徐々に復色するのを防ぐため、還元漂白剤は過剰に使われがちです。
● [亜硫酸塩]合成漂白剤――「亜硫酸塩」には、保存料としての効果の外に、「酸化防止剤」としての効果、「漂白剤」としての効果があります。主な使用食品は、かんぴょう、干しブドウを除く乾燥果実、コンニャク粉、ゼラチン、果実酒、雑酒、チェリー砂糖漬け類、水あめ、天然果汁、甘納豆、煮豆、エビ剥き身、冷凍イカ剥き身、などの多種があります。ラットでは多発性神経炎、骨髄の萎縮、催奇形性、代謝障害などが見られ、遺伝毒性が認められたととの報告があります。

| [OPP (オルトフェニルフェノール)] [OPP-Na] 合成防カビ剤 |
輸入されるレモンやオレンジ、グレープフルーツを代表する、柑橘類のすべてが対象商品となっています。遺伝毒性、発ガン性が認められています。輸入果実は長い船旅で送られてきます。この長い輸送期間中に白カビが発生するのを防ぐために使われます。収穫後の果実に、ワックスにOPPを加えて塗布したり、スプレーしたり、溶液に浸漬したりなどの方法がとられます。外国では食品添加物ではなく、ポストハーベストといって、収穫後に使われる農薬です。 |
| [TBZ(チアベンダゾール)] 合成防カビ剤 |
輸入果実の軸腐れと、緑カビを防ぐために使われ、柑橘類とバナナに限って使用が認められている。動物実験で、ヘモグロビン・ミクロマトクリット値の低下、肝グリコーゲンの欠如、嘔吐、めまい、肝臓毒、成長抑制などの症状が現れ、遺伝毒性の疑いもある。TBZは海外では、野菜をはじめコーヒー豆などにも使われている。また、輸入バナナにはミニ酸化鉄が保存料として使われていますが、これも毒性があり、米国では使用禁止となっています。 |
| [OP(ジフェニル)] 合成防カビ剤 |
輸入果実の緑カビ、青カビを防ぐために使われ、輸入のレモン、グレープフルーツ、かんきつ類に限って認められています。動物実験で肝臓障害、ヘモグロビン量の低下、腎臓・尿細管に異常、体重抑制、寿命の短縮などが見られている。 |
|
ごらんいただいたことを大変ありがたく感謝します。 |
|
||||
|
![]()
![]()


