���X�����Đ��ŐH�ׂ�I
�Ȃ������āA���ꂪ������ł��B
�V�Ղ�����������ł���I
�Ð|�Ђ��A���傤��Ђ��ɂ��I
�@
�i���j�L�@�Y�Ɓ@��؈�ǂ����
�t���傤��
�@

�@
���@�����̂��܂݂ɂ��ō��ł��I
���Ŗ��X�����ĐH�ׂ�̂���ԁI
�@
�t���I�͈�ʓI�ɂ͂��܂蒲�����������̂܂ܐH�ׂ�̂����������Ǝv���܂��B
�P�A�V�N�ȗt���I���悭�܂��B
�Q�A�ׂ��������L���C�ɂƂ�܂��B
�R�A��̔w�Ő��I�̍���������y������ނ��܂��B
�S�A�s���P�O�������炢�ɐ��ďo���オ��ł��B
�T�A���X�����ĐH�ׂ�Ɣ������������܂�
�@
�t���I�́A�{���̏{�͏��Ăł����A�n�E�X�͔|���ɂ���Ĉ�N���o����Ă��܂��B
�@
�t���傤���́A���傤�������w�̑傫�����炢�ɂȂ������ɁA�t�������܂��n�������̂ł��B
�s�����g�F�ɂȂ�̂������ŁA���X��������|�Ђ��ɂ��ĐH�ׂ܂��B
�@
�܂��A�t���傤���������Ƒ������n������̂ŁA�����ɓ��Ă��ɓ�͔|������傤��(�M���傤��)�́A�|�Ђ��ɂ���Ƃ��̐F�f�����ōg�F�ɂȂ�A�u�͂����݁v�Ƃ��ċ������ɓY�����܂��B
�@
�@
���@�É����́@�t���傤���̎��n�ʓ��{��
�@
����20�N�ɂ�����S���̗t���傤�����n�ʂ�2,175�g���ł��B
���̂����É����͂W�S�V�g���őS���P�ʂƂȂ��Ă��܂��B
�@
�t���傤�����n��
�P�ʁ@�É����@�R�X��
�Q�ʁ@��t���@�R�O��
�R�ʁ@��錧�@�P�T��
�u����20�N�Y�n����Y��ؐ��Y�v�_�ѐ��Y��
�@
�t���傤���̎��n�ʂ����{��̐É����B
�Ȃ��ł��É��s�암�̋v�\�n��́A���͂��̂悢���n�ƖL�x�ȓ��Ɨʂ������Y�n�ł��B
�@
�v�\�̗t���傤���́u���炩���v�A�u�݂��݂������v�A�u����₩�v�ƁA�O���q��������H���������ł��B
�܂��h�ݐ����W���Q�����Ȃǂ����E�ۍ�p�͂��ꂩ��̋G�߁A�H���ł̗\�h�ɂ��L���ł��B
�{���}�������A���АH�������É��̔_�|�i�ł��B
�t��ɐA�������I���U��������t���o���Ă��܂��B
�t���I�Ƃ����Ă��t��H�ׂ�킯�ł͂���܂���B
�V������W���ɂ����ĐA���������I�������ɗt��n�ʂ���o���Ă���̂ŁA���̐V����������H�ׂ悤�Ƃ������ł��B
�t���I�͍����I�ƈ���Ă܂�����قǐ������Ă��Ȃ��̂ŏ������炪�_�炩���̂������ł��B
�t���I�͉Ă̔��������H�ו��ł�
�@
���D���ȕ��́C���X�����Ă��̂܂܂ŁB
������Ƃ��������̂��܂݂ɁA��ϊ��܂��B
���D�݂ɂ��܂����A������Ƃ������Ă݂āC�����h�����ȂƎv������C�M���ɂ����点��ƁA�h���������܂��B
�@
�����āA�ЂƎ�Ԃ�����Ȃ�A�ݖ���Ð|�A�~�|�ɒЂ����肵�܂��B
���Ȃ݂ɁA�H��(��ʓI�ɐH�ׂ��镔��)�́A����ۂ̔��������ŁA�ΐF�̌s��t�͐H�ׂ܂���B
�@
���̂��߁A�t�̕������̂ĂĂ��܂����������̂ł����C�①�ɂɓ���Ă����ƁC���L���ʂ�����܂��̂ŁA�����̋C�ɂȂ�ď�́A�①�ɂɂ���Ă����Ƃ��������E�E�E
�@
�@
���@�y�t���傤���̌��ʁz
���傤���̐h�ݐ����̃W���Q���[�����܂��H�~���h���A�܂��A���ݍ�p�����Ȃ����܂��B
�������悭����̂Ŕ������A
���X�̑哤���V�`���≖����⋋���邱�ƂŌ��N�ێ���}��܂��B
�@
���@�y�I�ѕ��z
�t�̗��Z���A�s�̍g�F�̕����ƍ��̔����H�p�����Ƃ̐F�������͂����肵�Ă�����̗ǂ��A���������͂��܂�傫�߂����A�����Ƃ�Ƃ����݂��݂��������̂�I�т܂��傤�B
�@
���@�y�����̃q���g�z
�t���傤���̗t�̕����͐H�ׂ�܂��E�L��p������̂ŁA���˂ė①�ɂɓ���Ă����Ɨǂ��悤�ł�(�P�T�Ԓ��x)�B
�@
���@�y�ۑ��@�z
�t���傤���́A�����Ɏア�̂Ń|���܂ɓ���ė①�ɂɕۑ����܂����A�ቷ�ɂ��キ���܂�ۑ��������܂���̂ŁA���߂Ɏg������܂��傤�B
�@
�@
���@�t���傤������������y����
�@
���@���̂܂ܖ��X������
�t���傤���́A�Ȃ�Ƃ����Ă����X�����ĂȂ܂ŐH�ׂ�̂���ʓI�B
�P�A���傤���͐���āA��ł������Ŕ���ނ��܂��B
�Q�A���D�݂̗ʂ̖��X�����Ă��������܂��B
�@
�@
���@�t���傤���Ɩ��X
��ԃV���v���Ŕ��������H�ׂ₷�����@�ł�
�ށ@��
�E�t���I�E�E�E�K�ʁ@�@�E���X�E�E�E�͂��傤���̖{���ɍ��킹�Ă��p�Ӊ������B
����
�@�@�t���I�ɂ��Ă���ׂ���������菜���܂��B
�A�@�t���I���悭�D�≘����悭���Ƃ��܂��B
�B�@�t���I��������P�O�`�P�T�����ɐ�܂��B
�C�@���M�ɗt���I�Ɩ��X��t���ďo���オ��ł��B
�D�@�t���I�̍��̕����i�������j�ɖ��X���������オ�艺�����B
�@
���@�t���I�Ɩ��X�̌���
�Ă̏��������t���I�̊܂�ł���W���Q���[����K���m���N�g�����g�̂��ꎞ���ߊ��������o�����鎖�Őg�̂��₦�܂��B�����Ă�ł���܂��B
���X�Ɋ܂܂��哤���V�`�����G�l���M�[�ɂȂ�܂��B
�܂��A���X�Ɋ܂܂�鉖�����Ẳ����s����₢�܂��B
�W���Q���[���̐h�݂��H�~���h�����Ă���A�Ă̏����ɂ��H�~�s�U���������Ă���܂��B
�ăo�e�h�~�̐H�i�Ƃ��Ă����߂̗����ł��B
�@
�@
���@�t���傤���̓V�Ղ�
�Ă̂���₩�ȕ����Ƃ��Đl�C�̐H�ނł��B
���Ⴋ���Ƃ��Ă��邯��Ǐ_�炩���Ɠ��̐H���������A
���ꂩ��̋G�߂ɂ҂�����̐V���o�����ł��B
�ށ@��
�E�t���傤���E�E�E�W�{�@�@�E�o���X���C�X���E�E�E�Q�T��
�E���X�E�V�Ղ畲�E�g�����E�E�E�K��
����
�@�@�o�����ɂ݂��𔖂��ʂ�B
�A�@�t���傤���ɇ@�������B
�B�@�A�ɐ��ŗn�����V�Ղ畲������B
�C�@�����P�U�O�`�P�V�O170�x�ɔM���A�`�𐮂��Ȃ����Q���ԗg����B
���@���炩���ߗt���傤���ɐ荞�݂����Ă����A
�݂����͂���ł���g����ƔZ���Ȗ��킢���y���߂܂��B
���@�A�g�i�ׂɁj�A���̂��ꂢ��3�F���H�~��������t���傤���B
���̂܂ܐH�ׂ�ꍇ�ɂ́A�݂��Ƀ}���l�[�Y���������u�݂��}���v�����E�߁B
��l�͂������q�ǂ��ɂ��H�ׂ₷���l�C������̂ŁA���Ђ��������������B
�@
�@
���@�t���傤���̂��傤��Ђ�
���܂݂ɍō��ł��I
�t���I���ݖ��ɒЂ��Ă��������ŁA���̂܂܃{���{���H�ׂꂿ�Ⴂ�܂��B
�ށ@��
�E�t���I�E�E�E1���@�@�E���傤��E�E�E�Z�邾��
����
�@�@�t���I�͂P�{�Âɐ蕪���A�����Y��ɐB
�t�̕����͐藎�Ƃ��A���I�ƌs15cm���x�ɂ���B
�t�̕����͐藎�Ƃ��A���I�ƌs15cm���x�ɂ���B
�A�@�s���Ɣ����ɐ�B
���I�͐����f�ʂ��傫�������A�����Z����܂��B
���I�͐����f�ʂ��傫�������A�����Z����܂��B
�B�@�ЂƂÂ��J�ɐ��C���ӂ����܂��B
�C�@�Y��ȕr���̗e��ɗ��Ăċl�߂�B
�D�@���I�̕������S�����Ԃ�܂ł��傤������āA�①�ɂŕۑ��B
�傫���ɂ����܂����A�Q���`�P�T�ԂŊ����ł��B
�傫���ɂ����܂����A�Q���`�P�T�ԂŊ����ł��B
�E�@�h���������āA�H�ׂ₷���Ȃ��Ă���ΐH���ł��B
���̂܂܃{���{���H�ׂĂ��������B
����͗����̖�ł����v�ł�����
���̂܂܃{���{���H�ׂĂ��������B
����͗����̖�ł����v�ł�����
�F�@�c�������傤��́A�܂��t���I��Ђ���̂Ɏg���Ă��������A
�u�ߕ����Ɏg���Ă����������ł��B
�①�ɂŕۊǂ��Ă��������B
�①�ɂŕۊǂ��Ă��������B
�@
�@
���@�t���傤���̊Ð|�Ђ�
�y�ޗ��z
�E�t���傤��
�`�Ð|�`
�E�Đ|�E�E�E�Q�O�O�����A�@�E�����E�E�E�U�O�`�W�O�����@�E�݂��E�E�E�Q�O�����@�E���E�E�E�ЂƂ܂�
�`�Ð|�`
�E�Đ|�E�E�E�Q�O�O�����A�@�E�����E�E�E�U�O�`�W�O�����@�E�݂��E�E�E�Q�O�����@�E���E�E�E�ЂƂ܂�
�y�����z
�i�P�j�@�t���傤���́A�t�̕�����藎�Ƃ��B
�i�Q�j�@���I�̕������Y��ɐA��̔w�Ŕ��������藎�Ƃ������ƁA
�M���Ő��\�b䥂ł�B�i���D�݂�䥂łȂ��Ă����܂��܂���j
�i�R�j�@�Ð|�̍ޗ����ɓ���Ă����Ǝς������A
�O���X�Ȃǂɓ���āi�Q�j�̐��I������B
�O���X�ɐ��I������ƁA�݂�݂�s���N�F�ɐ��܂��Ă��܂��B
���@�t���傤�����͂�
�V������X���ɂ����Ă͗t���I�����n�ł��܂��B
�{�̂��̂��ȒP�ɔ��������H�ׂ�B
���ꂪ�t���I���тł��B
�ށ@��
�E�t���I�@�@�E���߁i�t���I�Ɠ��ʁj�@�@�E�ݖ��i���ʁj �@�E����
����
�@�@�t���I�̍��ƌs�����݂����ɂ��ď��M�Ɉڂ��܂�
�A�@�t���I�Ɠ��ʂ̊��߂����M�ɓ���܂�
�B�@�ݖ������ʂ����Ă悭�����܂�
�C�@���тɂ̂������ďo���オ��ł�
�@
�@
���@�t���傤���̐������݂���
�t���傤���̍��肪���܂�Ȃ����������ł��E
�ށ@��
�E�t���傤���E�E�E�Q�����@�@�E�ɂ�E�E�E�P/�Q�{�@�@�E�āE�E�E�Q�J�b�v
�E���E�E�E�傳���Q�@�@�E���傤��E�E�E�傳���P�@�@�E���E�E�E�Q�J�b�v
����
�@�@�Ă��Ƃ��A����ɂ����Đ�������B
�A�@�t���傤���E�ɂ�͂����ɂ���B
�B�@���ъ�ɕāE�t���傤���E�ɂ�E�������E�������A���邭�����Đ����B
�@
�@
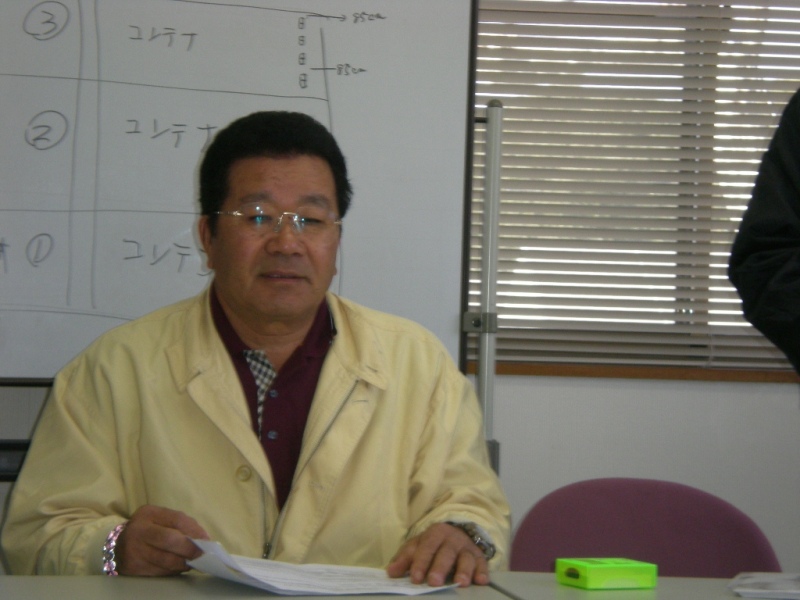
�@
�u�{��������܂��܂�����I
�@
�����́A���a�Q�Q�N���܂�A�w����A�Ȗ،��̃L���X�g���n�̎��R�w���ɓ����A�ߐ{���C�_��Ɋw�сA������A�ƋƂ̂����͔|���p���Ɠ����ɍD�����������̎���Ɏ��g�ݗ�ؖq����o�c����B
�@
��R�O�N�O�A�����́A�u���̕��A�������ǂ����邩?�v�@�ƍl���A�͔�Â�����n�߂��̂��A���݂̗L�@�Y�ƃV�X�e���J���̂��������ł����B
�@
�L�@�Y�Ƃ́A�É����̍œ�[�Ɉʒu���A�����������H�u�q�̌��C���^�[�`�F���W���o��ƈ�ʂ̒������A�Ȃ��n���L����A���Ȃ��ɂ͑����m��]�ނ��炵�����R���̉��g�Ȓn��ɂ���܂��B
�@
�u�����A�_�Ƃɂ�������́A�V��ٕςɂ��e������A�傫�ȕω��̌���������ƂȂ��Ă��邪�A�{�C���o���Ė{��������Ă����܂��܂�����čs���邵�A�t�ɖʔ������ゾ�v�@�Ɨ͐���������B
�@
�y�L�@�Y�ƃO���[�v�̌o�c���j�z
���@�L�@�Y�Ƃ͎��R���Ԍn�̖@�������ƂɁA���̎Y�Ƃł���_�ƂɎ��g���
���܂��B
���@�����h��y���̂��߂ɗǎ��ȑ͔�����Ă��܂��B
���@�͔|���@�����܂����ƂȂ��w���������܂��B
���@����ɂ����n�������Y����̔������Ă��������܂��B
���@�{���̃G�l���M�[����������Ƃ��̐��Y���@���Љ�ɔ��M���A���y�������s���܂��B
�@
�@
���R���Ԍn�̖@�������ƂɁA
���̎Y�Ƃł���_�ƂɎ��g��
�@
��؈�ǂ���͌���Ă��܂��B
�u�A�����������l�Ԃ��A���R�Ɗ�{�ɋt����Ă͂����Ȃ��B
���ׂĉF����Ԃ̒��ɑ��݂�����̂́A���̐ۗ��ɏ]���Đ��藧���Ă�����̂ł���A���R�̂̒��̏������������Ă͌����Ă������̂ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
���ɑ�ꎟ�Y�Ƃɂ����ẮA���R�̐ۗ��ɂ����ɏ������邩������v�ƁB
�@
������ɗ^���鎔���́A���猵�I�����V�R�̑f�ނ݂̂��g�p���܂��B
���̓V�R�f�ނɑ̂̏��ʂƊ������ʂ̂��銈���Y�ƁA���ʃ~�l�����ނ������������S���̍����Ǝ��̔z������������Ă��܂��B
�@
���̂��Ƃŋ��̓��������ꂢ�ɂȂ茒�N��Ԃ����シ��ƂƂ��ɁA�{�ɂɈ��L�͂Ȃ��Ȃ�A�����A���ǂ��͔�ƂȂ��ĊҌ�����A���ꂪ�܂����S���i���̔_�Y���ƂȂ萶�����z����B
�@
����ɗ����́A�����͔|�̐��Ƃ����ɐ��ւ̂��������[���A�Z���~�b�N�ƒY�f���g���Đ������A�����������~�l�����o�����X�̎�ꂽ���������������ɗ^���܂��B
�@
���̐��͐l�Ԃ̈������Ƃ��Ă����N���i�Ɍ��ʂ̂�����̂ł���A������R�[�q�[�ɁA�܂����т␆���A����A�����C�ɂ����ʓI�Ȃ��̂ł��B
�����āu�����Ȃ�ꍇ�ɂ��A�l�̂��߂ɂ��A�����̂��߂ɂ��A�앨�̂��߂ɂ��A���R�̖@���ɑ����Ċ�{���������肵�Ă��邱�Ƃ��厖���v�ƁB
�@
�@
����u���y��̒����ǂ��Ȃ��Ă���̂�
�u�앨�͐l�Ԃ̌����Ȃ�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�앨�̐���ɂ��킹�앨�̐����č앨�ɍ��킹��v�B
�ڂɌ����Ȃ����̕������ǂ��Ȃ��Ă���̂��A���̐A���̍����y��̒����ǂ��Ȃ��Ă���̂��B
�q�ǂ�����������ɂ��������ėv��������̂��ς���Ă���A�K�v�Ȃ��̂��ς���Ă���B
����Ɠ����悤�ɍ앨�͐����ɂ��������ċz��������̂��ς���Ă����B
�@
�u�앨�̐����ɍ��킹�P�������\�����ĕK�v�Ȃ��̂����ɗ^���Ă����B
���̂��ߖ����y����`�F�b�N���A�y�뒆�̐����o�����X�𐮂��Ă������Ƃ��v�Ƃ����B
�@
�u�A���Q�₻�̑��̕a�C�̌������A���̑����͍���y�̒��Ɍ���������A���������Ȃ���s�����Ȃ���y�𐮂���ɂ���v�B
�u�앨�ɍ��킹���y��Ǘ���������������A�g�}�g��L���[����ږ������A�y����ł����Ȃ��Ō��N�Ɉ炿�A�P�T�N�ԘA�삵�Ă���ޏ�ŁA�قƂ�Ǖa�C�ł���邱�Ƃ��Ȃ��v�Ƃ����B
�@
�����͍��͔���Ɩ�ؐ��Y�_�Ƃ⋍�̎���_�ƂȂǂ̑��k�ɉ�����̂ɑ����ł���B
���R���Ԍn�ɏ������������̔_�ƁA�z�^�_�ƃV�X�e���̊J�����y�Ɏg�����������Ċ�������́A�����̎d���������܂���������Ŗ����Ƃ������ł͂Ȃ��A���R�ւ̈،h�̔O�������āA���{�̏����̈��S�ň��肵���H�Ɛ��Y�Ɣ_�Ƃɂ����������R���ۑS�Ɏ��_��u���Ċ��鐶�Y�Ĕ_�Ƃł��茤���J���Ƃł���A���Ԍn�_�Ƃ̎w���҂ł���B
�@
���{�I�_�ƋZ�p�����E�̍Ő�[��
�����́A���R���Ԍn�@���ɑ�����"�悢�͔�Â���"����"�悢�앨�Â���"�̈�ё̐��V�X�e���́A���A������ό��ȂNJC�O��������ڂ����сA�w�����������ꑽ�Z���ɂ߂Ă���B
�����͌���
�@�u�������A���{�ɂ����錻�݂̔_�ƋZ�p�́A�a���Q�∫�V��ɉe�������n�ʂ��s����A������⒆�����͂��ߊC�O����̗A���U���ŁA���̂܂܂ł͓��{�_�Ƃ̌p������ςɊ�Ԃ܂�Ă���ł���B�v
�u�K�͓I�ɂ��l����I�ɂ��i�i�̍���������{�̔_�Ƃł͂��邪�A�������悸���̓��{�̐����Y�Ɓ��_�Ƃ��A���E�̍Ő�[���s�����D�ǂ̓��_�Z�p�Ƃ��Ă䂫�����B
���̂��߂ɂ́A�悢�͔�E�L�@�엿���g���āA�ʏ�̂Q�{����R�{�ȏ�̎��n�ʂ��グ�A����ɕa�Q���∫�V��ɉe������Ȃ������͂̋����앨�͔|�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v
�@
�s�n�͖L���Ȏ����\�Ȕ_�Ƃ̎����t
���{�̐��c�ɑ�\�����m�͂̐����Ȃ����l���_�Ƃ��A���ۑS�ʂ�����A�����Ĕ�������������A���z�I�Ȕ_�ƂƂ�����B
�@
�A��ɑς�����y��Â��肪�ł��Ă����A���S�Ŕ��������A�����Ď����\�ȉc�_�����������x���œW�J���čs����̂��B
�@
�A���̂̃G�l���M�[���ő���Ɉ����o�����Ƃ��A���̂܂܂Ƃ���Ȃ����������H����l�ԂɃG�l���M�[���݂Ȃ��点�邱�ƂɂȂ�B�i��H�����j
�@
�@
�M�����H����́u���v
�_�Ƃ�ʂ��āu������v��m��
�@
�s�_�Ƃ͍Ő�[�Y�Ɓt
�_�Ƃ��ł��t�����l�̍����Y�ƂɂȂ�B
���ۑS�A�S�g�̌��N�A���v�A���
�@
�s�_�Ƃ͐����Y�Ɓt
���̂���H���A���̂�����݁A���̂���S�����Ă����B
�l�X�������ā@�K���Ȑl���𑗂邽�߂ɕs���Ȃ��̂Ƃ��Ă̔_�ƁB
���̂��͂��̂���H���Ă����������Ȃ��B
�@

�ΐ쌧�F��
�L�@�_�Y���������ƎҐΐ쌧�F��ԍ��@No.1001